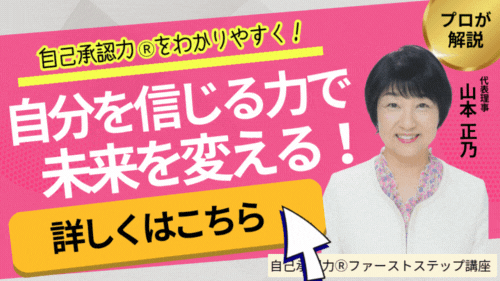いつも当協会のコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
自己承認力コンサルタント協会 代表理事の山本まさのです。
自己効力感(self-efficacy)とは、「自分ならできる」という感覚、すなわち課題達成への自信を指します。心理学者バンデューラは、自己効力感が高い人ほど困難な課題にも挑戦し、粘り強く取り組み、結果として成長しやすいと述べています。
私たち一般社団法人自己承認力コンサルタント協会では、この自己効力感を高めることが「自己承認力Ⓡ」を育むための大切な要素だと考えています。
自己承認力Ⓡとは、「自分を認め、自分を信じて前に進めるチカラ」。このチカラを伸ばすためには、自己効力感・自己肯定感・コミュニケーションスキルの3つをバランスよく育てる必要があります。
今回は、自己効力感を形作る4つの要因と、実践の方法をお伝えします。
自己効力感を形作る4つの要因
達成経験(成功体験)
実際に成功した経験は、最も強力に自己効力感を高めます。小さな成功でも「やればできる」という感覚を積み重ねることで、自信が育まれます。
教育現場の例:算数が苦手な児童に、まずは簡単な計算問題を解かせ、成功体験を積ませることで「できる!」という感覚が芽生えます。
ビジネスの例:新人社員に小さな業務を任せて成功させることで、自信と責任感が育ち、より大きな業務に挑戦する意欲が高まります。
代理体験(他者の経験から学ぶ)
自分と似た人が成功する姿を見ることで、「自分にもできるかも」と思えるようになります。
教育現場の例:同じクラスの友達が、発表会で堂々と発表する姿を見て「自分も挑戦しよう」と思える子どもは多いものです。
ビジネスの例:先輩社員が成功体験を共有することで、後輩が挑戦する勇気を持ちやすくなります。
社会的説得(言語的説得)
周囲からの励ましや肯定的な言葉は、自己効力感を押し上げます。特に信頼する人からの言葉は大きな影響力を持ちます。
教育現場の例:「あなたならできるよ!」という教師からの一言で、子どもが苦手な課題に挑戦するきっかけになります。
ビジネスの例:上司が「この案件、君に任せたい」と期待をかけると、社員のやる気がぐっと高まります。
生理的・情動的状態(情緒的喚起)
心や体の状態は、自分の力をどう感じるかに影響します。ストレスが高いと「できない」と思いやすくなり、心身が整っていると「できそう」と感じやすくなります。
教育現場の例:試験前に深呼吸やストレッチを行うと、緊張が和らぎ実力を発揮しやすくなります。
ビジネスの例:プレゼン前に軽い運動やポジティブな言葉を口にすることで、落ち着いて本番に臨めます。
明日からできる!実践ガイド5選
小さな成功リストを作る
過去にできたこと・達成したことを10個書き出しましょう。成功体験を思い出すことで「やればできる」という感覚が蘇ります。
ロールモデルを見つける
「自分に似た人」で成功している人を探し、その行動を観察しましょう。「あの人ができたなら、自分もできるかも」と思いやすくなります。
フィードバックを受け取る
信頼できる人に「自分の強みを3つ挙げてください」とお願いしてみましょう。他者の視点で自分の価値を再発見できます。
心と体を整える習慣を持つ
深呼吸、軽い運動、ポジティブな言葉がけなど、自分を落ち着かせる方法を1つ決めましょう。緊張や不安を前向きなエネルギーに変えられます。
できたこと日記を書く
毎晩、今日できたことを3つ書きましょう。達成経験の積み重ねが、確実に自己効力感を育てます。
協会での実践:自己承認力Ⓡとの関係
自己効力感を高める4つの要因は、協会が伝える自己承認力Ⓡの実践と深く結びついています。
– 小さな成功体験を積む → 自己効力感が上がり、「自分を信じる力」が育つ
– ポジティブな言葉を交わす → 自己肯定感が高まり、人間関係が良くなる
– 挑戦しやすい環境を整える → スキルと自信の両方が伸びる
協会の研修や講座では、これらを意識したワークを行い、受講者が自分の変化を実感できるようにしています。
まとめ
自己効力感は、「達成経験」「代理体験」「社会的説得」「情動的状態」の4つの要因から形成されます。この4つを意識的に満たすことで、「自分ならできる」という感覚が高まり、人生のあらゆる場面で挑戦しやすくなります。
私たちの協会では、自己効力感を高めることが自己承認力Ⓡを伸ばすための重要な一歩であると考えています。今日ご紹介した5つの実践を、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。
小さな実践が、自信や安心感につながっていきます。最後までお読みいただき、ありがとうございました。