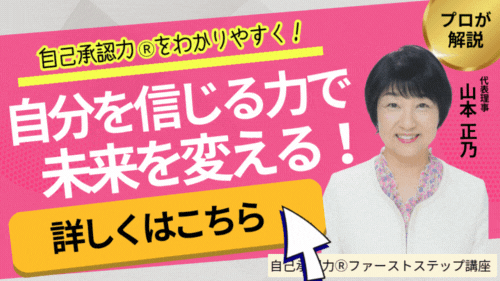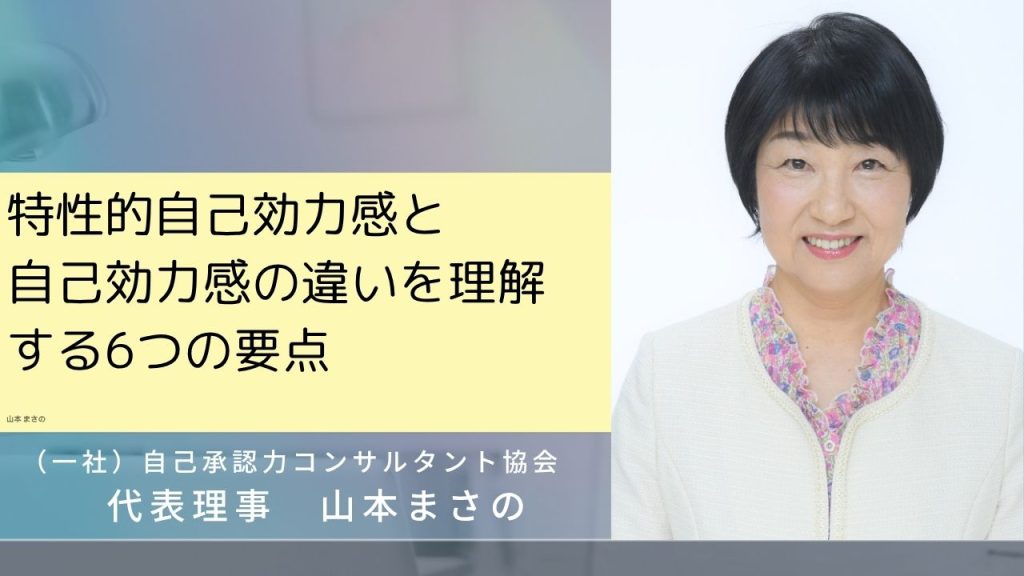
~自信が育ち、行動が変わる“心の仕組み”~
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
一般社団法人自己承認力コンサルタント協会 代表理事の山本まさのです。
人は日々、小さな挑戦を積み重ねながら生きています。
「できるかな?」と思う瞬間もあれば、「やってみよう!」と前向きになれるときもあるでしょう。
その心の揺れを支えている心理的エネルギーが 自己効力感です。
今回は、専門的な心理学の知見も踏まえながら、
「特性的自己効力感」と「自己効力感(状態)」の違いを6つのポイントでわかりやすく解説します。
違いを理解すると、自分の行動のクセが分かり、
自信を育てるための具体的な方法が見えてきます。
そもそも自己効力感とは何か?
自己効力感(Self-Efficacy)とは、
心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念で、
「自分はこの課題を達成できる」、と信じる力のことです。
自己効力感は、行動の“エンジン”ともいえる存在。
この感覚が高いほど、
- 新しいことに挑戦しやすい
- 行動が長続きしやすい
- 困難に直面したときに折れにくい
といった特徴があります。
しかし、多くの人が誤解しがちなのは、
自己効力感は「性格」ではなく、その場・状況で変動する心理状態であるという点です。
同じ人が、ある場面では「できる!」と思えるのに、
別の場面では「無理かも…」と感じることがありますよね。
これが「状態としての自己効力感」です。
特性的自己効力感とは“性格的な自信の傾向”のこと
一方で、「特性的自己効力感」という概念があります。
これは、
状況が変わっても比較的安定して持ち続ける“性格的な自信の傾向”
を指します。
たとえば、
初めての環境でもあまり動じない人、
難しい課題にも前向きに取り組む人、
失敗しても「またやってみよう」と切り替えが早い人。
こうした“自信のクセ”のようなものが、
特性的自己効力感です。
状態としての自己効力感が「波」だとすると、
特性的自己効力感は「海の深層流」のようなもの。
表面の波は揺れても、深い部分には一定の力が流れている——そのようなイメージです。
2つの違いは「変わりやすさ」と「形成過程」にある
では、この2つはどのように違うのでしょうか?
◆変動しやすさ
- 自己効力感(状態):すぐに上下する
- 特性的自己効力感:長期的に安定している
たとえば、人前で話すのは苦手でも、料理なら自信がある人もいます。
これは「状態としての自己効力感」が場面によって変わるためです。
◆ 形成される期間
- 状態の自己効力感:日々の小さな成功・失敗で変動
- 特性的自己効力感:幼少期からの経験、失敗と挑戦の積み重ねで形成
◆役割
- 状態の自己効力感:今日の行動に影響する“調子”のようなもの
- 特性的自己効力感:長期的な挑戦姿勢や生き方を支える“土台”
この違いを理解すると、
成長のためにはどちらも大切で、どちらも高められる
ということが分かります。
自己効力感は4つの経験から育つ
バンデューラは、自己効力感が高まる4つの要因を示しています。
成功体験(Mastery Experiences)
小さな達成の積み重ねが一番効きます。
「できた!」という感覚が自信の“核”になるためです。
代理体験(Vicarious Experiences)
自分に似た人の成功を見て
「私にもできるかも」と思える感覚。
言語的説得(Verbal Persuasion)
「あなたならできるよ」「ここまで来たじゃない」
という周囲の励ましやフィードバック。
生理的・情動的状態(Physiological & Emotional States)
不安が強すぎると自己効力感は低下し、
リラックスしていると「できる」と感じやすくなる。
これらは状態の自己効力感を高める要因ですが、
積み重なることで特性的自己効力感の土台も厚くなっていきます。
特性的自己効力感が高い人の特徴
特性的自己効力感が高い人には、共通した振る舞いがあります。
◆難しい課題にも前向き
「やってみよう」という姿勢が強い。
◆失敗しても回復が早い
落ち込んでも、長く引きずらない。
「次、どうする?」と切り替えられる。
◆主体的に行動する
受け身ではなく、自ら動いて結果をつくる。
◆ 初めての場面でも臆しない
未知の状況でもチャレンジする力がある。
◆自分の成長を信じている
「今できなくても、できるようになる」と考えられる。
これはまさに、協会でお伝えしている
「自己を認め、自分を信じて前に進めるチカラ」=自己承認力Ⓡ
と深くつながっています。
自己承認力Ⓡで2つの自己効力感を育てる方法
協会のメソッドは、
状態としての自己効力感と、特性的自己効力感の両方を強めることを目的としています。
以下は、日常でできる6つの実践です。
“できたこと”を言語化する
「できたこと日記」など、小さな達成を記録する習慣が
自己効力感の最も強力な強化方法です。
マイクロゴール(超小さな目標)を設定する
成功体験を細かく積み重ねることで、
今日の自己効力感(状態)も、長期的な土台(特性)も高まります。
比較は“他人”ではなく“昨日の自分”
人と比べる癖を減らし、
「前の自分より少し進んだ」ことに目を向けると自信が安定します。
フィードバックを受け取る練習をする
周囲からの言語的説得は、自信のエネルギーになります。
「ありがとう」「助かったよ」を受け取りやすくなることは、
自己承認力Ⓡの基盤でもあります。
情緒を整えるセルフケアを習慣にする
不安・疲労・緊張は、自己効力感を押し下げます。
睡眠・休息・リラクゼーションを整えることも重要な要素です。
小さな挑戦を日常に置く
- 新しい道を歩く
- いつもより少し早起きする
- 1つ仕事のやり方を変える
このような「小さな新しい行動」が、
自己効力感の“筋トレ”になります。
まとめ:2つの自己効力感の違いを知ることが、自分を前に進める力になる
- **自己効力感(状態)**はその場ごとに変動し、
- 特性的自己効力感は長期的に安定した自信の傾向。
しかし、どちらも後天的に育てることができます。
自己承認力Ⓡの3つの柱
「自己肯定感」「自己効力感」「スキル」 を同時に高めることで、
自分を信じて前へ進める強い心の土台がつくられます。
人生のあらゆる挑戦は、
「自分ならできる」という小さな一歩から始まります。
これからも一緒に、その一歩を育てていきましょう。