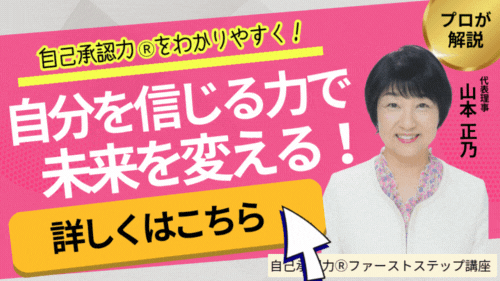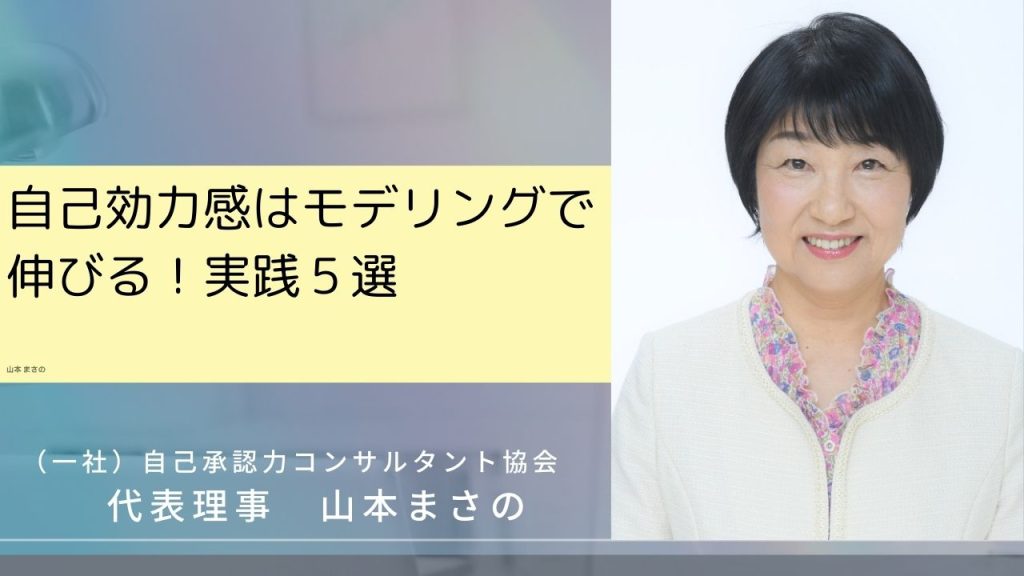
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
自己承認力コンサルタント協会 代表理事の山本まさのです。
「やればできる!」――そう思える力を心理学では【自己効力感(Self-Efficacy)】と呼びます。自己効力感とは、心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念で、人の挑戦や行動のあり方を大きく左右するものです。自己効力感が高い人は困難に果敢に挑戦し、失敗しても立ち直り、最終的に成果を手にします。一方、自己効力感が低い人は「どうせ自分には無理」と考えてしまい、挑戦する前に諦めやすくなります。
当協会が提唱する「自己承認力Ⓡ」とは、自分を認め、自分を信じて前に進めるチカラです。その柱は、①自己肯定感、②自己効力感、③スキル(特にコミュニケーション力)の3つで成り立っています。中でも自己効力感は「やればできる!」と信じて挑戦し続けるための心理的基盤であり、自己承認力Ⓡを育むうえで欠かせない要素です。
バンデューラは、自己効力感を高める4つの源として「達成経験」「代理経験(モデリング)」「言語的説得」「生理的・情動的状態」を挙げています。その中でも【代理経験(モデリング)】は、子どもから大人まで誰にでも働く強力な心理的メカニズムです。
「人の成功する姿を見て、自分もできると信じられるようになる」――他者の挑戦や成長の姿が、自分の自己効力感を押し上げるのです。
モデリング実践5選
ロールモデルを見つける
自己効力感を高める第一歩は、自分にとって参考になるロールモデルを見つけることです。必ずしも偉大な人物でなくても構いません。職場の先輩や友人、SNSで発信している人、書籍の著者など、「自分と似た環境で努力している人」の存在は大きな力になります。
たとえば、同じ部署の先輩が苦手だったプレゼンを克服して成果を出した姿を見て、「自分も挑戦してみよう」と勇気を持てることがあります。近い立場の人ほど、「自分にもできそうだ」という実感につながりやすいのです。
成功のプロセスを観察する
成功を観察するときは「結果」だけに目を向けるのではなく、「そこに至るプロセス」に注目することが重要です。成功した人がどのような工夫をしたのか、どんな手順を踏んだのかを知ることで、自分が取り入れられる行動のヒントが得られます。
たとえば、資格試験に合格した友人に「毎日どのくらい勉強していたの?」と聞いてみると、「一日30分だけど必ず続けた」という答えが返ってくることがあります。大きな成果の裏には、意外にも小さな習慣の積み重ねがあるものです。
失敗からの立ち直りを学ぶ
モデリングは成功だけでなく、失敗からの立ち直りを観察することでも大きな力を発揮します。誰もが順風満帆に成功できるわけではありません。むしろ、失敗を経験しながらも再挑戦する姿は、大きな勇気を与えます。
例えば、営業活動で契約を取れなかった先輩が落ち込むのではなく、次回に向けてトークを改善し、再び挑戦して契約を獲得したとします。その姿を見た新人社員は「失敗してもやり直せばいい」と安心し、前向きに行動できるのです。
仲間と挑戦を共有する
一人でロールモデルを探すだけでなく、仲間と挑戦を共有することも効果的です。仲間同士で成功体験をシェアすることで、互いが互いのロールモデルとなります。
当協会の講座や「できたこと日記」では、参加者同士が日々の実践や気づきを共有する仕組みを大切にしています。たとえば「今日は会議で意見を一つ言えた」という小さな報告が、別の人にとっては「自分もやってみよう」と挑戦するきっかけになります。誰かの小さな成功が、仲間全体にポジティブな波及効果をもたらすのです。
⑤ 自分が誰かのモデルになる
最後に、自分自身が誰かのモデリングの対象になることも大切です。「自分なんて」と思うかもしれませんが、あなたの小さな行動や挑戦が、実は周囲に大きな影響を与えます。
たとえば、会議で普段は発言しない人が一度だけ意見を述べたとき、それを見た後輩が「自分も発言してみよう」と思えることがあります。また、子どもの前で親が新しい趣味に挑戦する姿を見せるだけでも、挑戦する勇気を自然と伝えられるのです。人に教えたり体験を発表したりすることで「見られている」意識が生まれ、それが自己効力感をさらに強化する好循環をつくります。
自己効力感とモデリングの関係
モデリングとは「他者の行動を観察し、その結果を学ぶこと」です。人間は単に自分の経験から学ぶだけでなく、他者の経験を観察することで効率的に学習できます。
例えば、同じ職場の仲間が成功した姿を見て「自分もやってみよう」と思えることがあります。特に「自分と似た人」の成功は効果的です。年齢・性別・環境が近い人が困難を克服する姿は、「自分にもできるかもしれない」という感覚を生み、自己効力感を押し上げます。
教育現場では、クラスの誰かの成功が波及し、他の児童が挑戦に踏み出す姿がよく見られます。ビジネスの場では、先輩社員の実演が新人の挑戦意欲を刺激します。家庭では、親の挑戦する背中が子どもに大きな学びを与えます。
具体事例
教育現場
- 発表が苦手な児童が、クラスメートの堂々とした発表を見て「自分も挑戦してみよう」と手を挙げました。その一歩が成功体験となり、積極的に発言できるようになりました。
- 受験勉強をあきらめかけていた高校生が、同じ部活動の友人がコツコツ勉強する姿を見て「自分もやってみよう」と学習時間を増やし、最終的に合格を勝ち取った。
ビジネス
- 営業の新人が「自分には契約は取れない」と悩んでいたとき、先輩の顧客対応を見学しました。質問に誠実に答え、不安を丁寧に解消する姿を観察し、「自分にもできる部分がある」と感じ、自信を持って商談に臨むことができました。
- 管理職候補の社員が、大きなプレゼンに挑戦する前に上司の練習風景を見学。何度もリハーサルを重ね、修正していく姿を知り「完璧な人も努力を重ねている」と学び、自分の準備にも集中できるようになった。
子育て
- 「挑戦しなさい」と言葉で伝えるだけでは効果が薄いことがあります。しかし、親が「失敗しても大丈夫」と挑戦する姿を見せれば、子どもは自然とその姿を真似ます。「親の言葉より行動が教育になる」――これもモデリングの力です。
- 母親が料理教室で新しいメニューに挑戦している姿を見た子どもが、家で「自分もやってみたい」と手伝い始め、やがて自分で簡単な料理を作れるようになった。
スポーツ
サッカー部の一年生が試合でうまく動けずに落ち込んでいたとき、二年生の先輩が失敗を恐れず全力でプレーする姿を見て「自分も思い切ってやってみよう」と積極的にボールに向かうようになった。結果として試合への参加意欲が増した。
地域活動
町内の清掃活動で、高齢の方が黙々とゴミ拾いを続ける姿を見て、若い世代が「自分もやらなくては」と参加するようになり、地域全体の雰囲気が明るくなった。
医療・介護
リハビリを受けている患者が「もう歩けない」と思っていたが、同じ病室の仲間が少しずつ歩けるようになる姿を見て、「自分もやればできるかもしれない」と挑戦。小さな一歩を踏み出せた。
このように、モデリングは教育・ビジネス・子育てだけでなく、スポーツや地域、医療の場面でも幅広く作用します。
「誰かの姿を見て自分もやってみよう」と思える循環が生まれると、自己効力感だけでなく自己承認力Ⓡ全体が育まれていくのです。
実践ワーク
モデリングは「他者の行動を観察し、自分もできると思えるようになる」強力な方法です。自己効力感を高め、ひいては自己承認力Ⓡを育むために欠かせません。
今日からできるアクションを3つご紹介します。
- 身近なロールモデルを1人見つける
家族・職場・友人などから「この人のやり方を真似してみたい」と思える人を探す。 - その人の行動手順を観察・記録する
「なぜうまくいったのか?」を具体的に書き出す。 - 明日、自分なりに小さな実践を試す
観察したポイントを自分の生活に取り入れ、「できたこと日記」に記録する。
このサイクルを繰り返すことで、自己効力感と自己承認力Ⓡが同時に高まっていきます。
まとめ
モデリングとは、他者の姿を通して「自分にもできる」と信じられるようになる力強い方法です。誰かの挑戦を観察し、その工夫や姿勢を自分の行動に取り入れることで、自己効力感が高まります。さらに、やがて自分自身も誰かのロールモデルとなり、その姿がまた他の人の力になる――そんな循環が生まれていきます。
自己効力感は、自分一人で努力して育てることもできますが、他者の存在を通じてこそ大きく伸ばすことができるものです。身近な周りを見渡せば、必ず参考になる人がいます。そして同時に、あなた自身の姿も、きっと誰かにとっての学びや励ましになっているのです。
「人の挑戦から学び、自分の挑戦を誰かに見せる」――この相互の循環こそが、自己承認力Ⓡを高め、人生をより豊かに切り開いていく原動力となります。