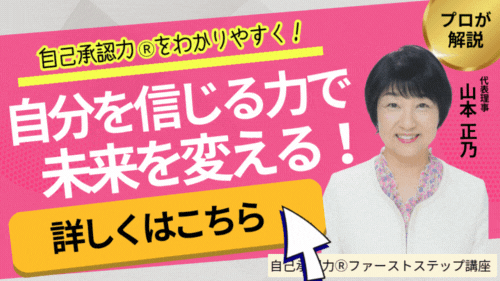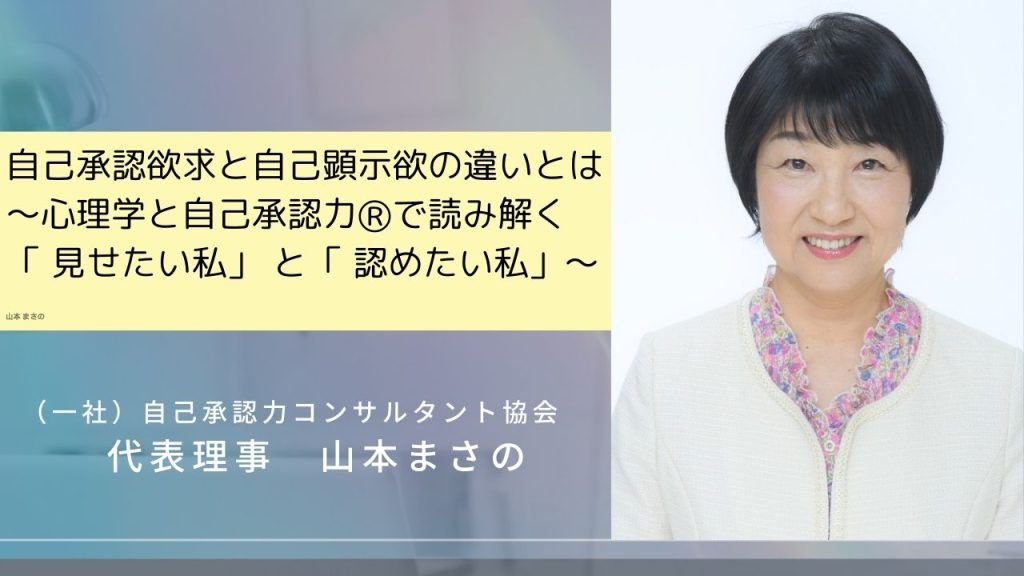
いつもコラムをお読みくださり、ありがとうございます。
自己承認力コンサルタント協会 代表理事の山本まさのです。
このコラムでは、「自己承認力®」に関するさまざまなテーマを取り上げながら、
皆さまからの疑問や関心に、できるだけ分かりやすくお伝えしています。
現代のSNS社会において、「評価されたい」「目立ちたい」という欲求は、誰の中にも少なからず存在します。しかし、それが本当に心から求めている承認なのかどうか、立ち止まって見つめ直すことが必要です。
今回は、似て非なる2つの心理的欲求――自己承認欲求と自己顕示欲――の違いと、それぞれとどう向き合うべきかを、心理学と自己承認力Ⓡの観点からお伝えします。
心理学で解説~自己承認欲求「自分で自分を認めたい」とは?

「自己承認欲求」とは、自分の存在や行動、努力に対して、自分自身が納得し、価値を見出したいという欲求です。
これは心理学者アブラハム・マズローの「欲求5段階説」の第4段階「承認・尊重の欲求」における内的承認に該当し、他者の評価に頼らず、自己評価や内省を通じて心の安定感を得るプロセスです。
承認欲求は2種類に分かれる
- 他人からの評価や賞賛を求める(外的承認):上司から評価される、同僚から認められる等で満たされる
- 自己評価を重視し、自分自身を認める(内的承認):自己の成長や貢献を自分で評価することで、満たされる
たとえば、
- 「今日はしんどかったけど、最後まで頑張った私、偉い」
- 「結果は出なかったけど、挑戦した自分を褒めたい」
このようなつぶやきは、健全な自己承認欲求の表れです。
この内発的な承認が満たされていくと、自然と自己肯定感や自己効力感が育まれ、ブレない自分軸を形成していくことができます。
自己顕示欲「他人に認められたい」「称賛されたい」という外的承認欲求
一方、自己顕示欲とは、自己の存在や成果を周囲に示し、他者からの称賛や注目を得ようとする欲求です。
「SNSで“いいね”が欲しい」「誰かにすごいと思われたい」などの欲求は、外的承認への依存傾向を強めるものです。
この自己顕示欲は、適切に活用すれば
- 行動意欲の向上
- 自己表現力の発揮
- 持続可能な目標達成のモチベーション
につながります。しかし、過度になると、
- 「見られていないと不安」
- 「評価されないと自信が持てない」
- 「虚像の自分を演じ続けて疲弊する」
といった承認依存症に陥るリスクがあります。
混同しがちな2つの欲求の違いとは?
| 比較項目 | 自己承認欲求 | 自己顕示欲 |
| 欲求の方向 | 内面(自己評価) | 外面(他者評価) |
| 満たし方 | 内省・納得・実感 | 反応・称賛・注目 |
| 心の状態 | 安定・静かな満足 | 一時的高揚・不安定 |
| 主なリスク | 自己否定感の克服が必要 | 承認依存・虚像疲労 |
現代社会では、SNSや情報発信を通じて、自分を見せることが推奨されがちです。ですが、本当の意味で満たされるのは「内なる自己が納得しているかどうか」ではないでしょうか?
自己承認欲求は、自己成長を内的に支える燃料であり、自己顕示欲は、外的刺激による加速装置のようなもの。
どちらが悪いということではなく、どちらを主軸に生きているのかが重要なのです。
自己承認力を高めることで、顕示欲と上手に付き合う
では、どうすればこの2つとバランスよく付き合っていけるのでしょうか?
鍵になるのは、「自己承認力Ⓡ」を育てることです。
当協会が提唱する「自己承認力Ⓡ」とは、
「自分を認め、自分を信じて前に進めるチカラ」
(※商標登録済)
このチカラは、以下の3要素を同時に育てることで高まります:
- 自己肯定感:あるがままの自分を否定しない
- 自己効力感:できると信じて挑戦する力
- スキル(特にコミュニケーション):自分の気持ちを適切に伝える力
これらを日常の中で意識的に育てることで、
「他人からの承認がなくても、自分の中に確かな実感がある」
という“内発的な安心”が得られます。
まとめ――「見せる私」より、「信じる私」へ
現代は「見せる自分」を演出することが評価されやすい社会です。しかし、他人の目に依存した自己像は脆く、不安定になりやすいものです。
「誰かに見せるための自分」ではなく、「自分で納得できる私」でありたい。
そう願うあなたには、ぜひ**自己承認力Ⓡ**を育ててほしいと思います。
自己顕示欲は、一時的な満足や行動のきっかけになります。
しかし、真の安心感や継続的な自信は、自己承認欲求が満たされたときに育まれるものです。
他人の目に頼らず、自分で「私は大丈夫」と言える心を育てていきましょう。