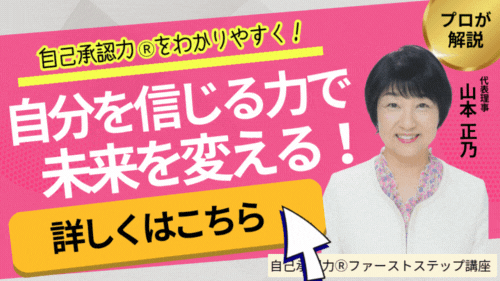いつもコラムをお読みくださり、ありがとうございます。
自己承認力コンサルタント協会 代表理事の山本まさのです。
当協会では、「自分を認め、自分を信じて前に進めるチカラ=自己承認力Ⓡ」を高めるための講座や研修を通じて、皆さまの内面の安定と行動力向上をサポートしています。
「もっと認められたい」「頑張っている私をわかってほしい」
そんなふうに感じることはありませんか?それは、決して弱さではなく、誰もが本能的に抱く“自然な心の動き”です。
心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求階層説」においても、承認欲求は「尊厳の欲求」とされ、人間の成長や自己実現に欠かせない要素とされています。
けれどこの欲求が他者頼りになってしまうと、評価されなければ不安になる「承認中毒」に陥ることも……。
大切なのは、「他人に求める承認」ではなく、「自分で自分を認める=自己承認」によって、この欲求を満たすことです。
🔹事例:会社員のAさん(40代・女性)
上司からの評価に一喜一憂し、ミスをすると「もうダメだ…」と落ち込んでいたAさん。
当協会の講座で「自己承認力Ⓡ」を学び、夜に日記をつけて自分の努力を認める習慣を始めました。半年後、「誰かの一言で気持ちが上下することが減りました」と話してくれました。
このように、自分で自分を承認する力を身につけることは、心の安定と成長に直結します。
本コラムでは、心理学の理論と当協会の実践的メソッドをもとに、「自己承認欲求を自分で満たす」方法を体系的にお伝えします。
自己承認欲求を満たす方法5つ
CBT(認知行動療法)を活用する
- 「自分はダメだ」といった自動思考を書き出し、「本当にそうか?」と問いかけて修正します
- 行動実験によって、「自分は評価されない」という思い込みを実体験で見直します
- 日記によるセルフモニタリングで、心の状態を“見える化”しましょう
🔹事例:販売職のEさん(20代・男性)
クレーム対応に失敗した日、「自分は接客に向いていない」と落ち込みましたが、日報に「お客様の怒りに冷静に対応できた点はよかった」と書き出すことで、自己評価を少しずつ修正していきました。
誤った習慣に気づく
- SNSでの“承認トラップ”に要注意!「いいね」数=自分の価値、ではありません
- 「他人と比較する癖」「完璧主義」「空気を読みすぎる」などは、自己承認の妨げになります
🔹事例:高校生のFさん(10代・女性)
SNSのフォロワー数に敏感で、自撮りばかり投稿していたFさん。
講座で「本当に届けたいのは何か?」を見直し、絵の投稿に切り替えると、「承認されたい」より「表現したい」が強くなったと語っています。
セルフコンパッション(自己への優しさ)
心理学者クリスティン・ネフ博士が提唱する「自分への慈しみ」の実践。
「今日つらいのは仕方ない」「私なりに頑張ってる」と声をかけましょう。
🔹事例:育児中のGさん(30代・女性)
子育て中のイライラに悩んでいたGさんは、「つらいのは当然、頑張ってるんだから」と毎晩声をかけるようになり、自己否定が減ったそうです。
感謝日記と自己褒賞
毎日寝る前に「今日嬉しかったこと」を3つ書く。
成功や努力には、小さなご褒美を!自分を認める具体的な行動です。
🔹事例:会社員のHさん(40代・男性)
毎晩「今日できたこと」を3つ書くうち、「自分って結構頑張ってる」と思えるようになり、以前より笑顔が増えたと同僚から言われたそうです。
マインドフルネス瞑想
・目を閉じて、5分間「呼吸」だけに集中
・評価や不安を手放し、「今ここ」に意識を戻す訓練になります
呼吸に意識を向けて、「今ここ」に集中することで、他者の評価から距離をとれます。
心理学から見た「自己承認欲求」とは?
心理学者マズローの「尊厳の欲求」とは何か?
マズローの理論では、承認欲求は「他者から認められたい」という外的な側面だけでなく、「自分で自分をどう見ているか=内的承認」も含まれています。
実際、私たちは“誰かの評価”よりも“自分自身の評価”に一番左右されているのです。
🔹事例:主婦のBさん(50代)
家族からの「ありがとう」がないことに不満を感じていたBさん。
講座を通じて「今日も家族のためにご飯を作った私、えらい!」と自分に声をかける習慣を始めたことで、イライラが減り、家族にも穏やかに接するようになりました。

外的承認 vs. 内的承認の心理的影響
- 外的承認(1)に依存しすぎると、評価が得られないときに不安定になりやすい
- 内的承認(2)がある人は、評価されなくてもブレずに前を向ける
自己概念とアイデンティティ
自己承認欲求が満たされにくいと、「自分とは何者か?」という自己概念が揺らぎ、結果として他人軸に振り回されやすくなります。
自己承認がもたらす心理的メリット
自己肯定感が高まる
「私は私でいい」と思えるようになり、過度な劣等感や他者との比較から解放されます。
🔹事例:起業家のCさん(30代・男性)
SNSでの「いいね」の数が気になり、自分らしい発信ができなかったCさん。
「自己承認日記」をつけることで「今日は自分らしい投稿ができた」という実感を育み、フォロワー数よりも内容に集中できるようになりました。
レジリエンス(心の回復力)が育つ
自分で自分を認めている人は、失敗や批判からの立ち直りが早く、折れにくい心を育てられます。
🔹事例:小学校教師のDさん(60代・女性)
授業で失敗したときに「私は教師として失格かも」と思っていたDさん。
自己労いの言葉「それでも準備は本当に頑張ったよね」と自分に言うことで、翌日は気持ちを切り替えて教室に立てるようになったそうです。
内発的動機づけが高まる
他人に褒められたくて行動するのではなく、「自分がやりたいからやる」という、ブレない軸ができます。
まとめ:他人に振り回されない「自分軸」を育てよう
自己承認欲求は、誰もが持っている健全な欲求です。自己承認欲求が満たされると、人生のあらゆる局面で自分を支える事ができるようになります。
当協会が提唱する「自己承認力Ⓡ」は、
- 自己肯定感(ありのままの自分を認める力)
- 自己効力感(未来の自分を信じて行動できる力)
- スキル(特にコミュニケーション能力)
という3本柱によって、自分を内側から満たし、前に進める力を育てていきます。
🔹最終事例:60代男性のIさん(企業役員)
人前で話すのが苦手だったIさんは、「私でいい」と思えるようになったことで、役員会でも堂々と話せるようになりました。
本記事で紹介した心理学的アプローチやセルフケアの実践は、エビデンスに基づいた方法ばかりです。
ぜひ、少しずつ日常に取り入れてみてください。
他人の評価に振り回されず、自分で自分を認め、信じる力を高めていくことで、心は驚くほど安定し、あなた本来の魅力が花開くはずです。