こんにちは!自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
「リーダーを任されたけれど、何から始めればいいのかわからない」
「経験がない自分に、人を導くなんてできるのだろうか」
そんな不安を抱えている方はとても多いものです。
リーダーシップは、生まれ持った才能や特別なスキルではなく、誰でも身につけられる「在り方」です。
特に経験が浅いリーダーほど、まっすぐに一人ひとりと向き合える誠実さとエネルギーがあります。それは、組織にとってかけがえのない強みです。
今回は、経験ゼロでも今すぐ実践できる5つのリーダーシップをご紹介します。

なぜ今、「リーダーシップ」が問われているのか
働く環境がめまぐるしく変化する今、職場では年齢も価値観も働き方も多様化しています。
上司が一方的に指示を出し、部下が動く…そんな時代は終わりました。チームをまとめるために必要なのは、強いリーダーではなく、“共に考え、共に動くリーダー”です。
リーダーシップとは、「人の心を動かし、関係をつくる力」と言えるかもしれません。そして人間関係の信頼の源になるのが、自己承認力です。「自分を認め、信じて、前に進める力」です。自分を整えられる人は、人を尊重できます。だからこそ、リーダーシップの第一歩は、外に向かう前に「自分を整える」ことなのです。
私は20代前半の頃、飲食店のアルバイトから社員に登用されました。
当時はまだ社会人経験も浅く、右も左もわからない状態でしたが、社員になった瞬間、周囲からの目が一気に変わりました。パートの方々からは毎日のように「社員なんだからしっかりして」「社員なんだからあなたがやって」と言われ、役割を全く果たせずに自信がなくなる日々。
そんな足りない自分を挽回するために、「リーダーシップを発揮しなくちゃ」と必死になっていました。
しかし、今振り返ると、その時の私は“リーダーシップの意味”を勘違いしていたのです。
「人を引っ張る」「指示を出す」「誰よりも前に立つ」それがリーダーシップだと思い込んでいました。
けれど、経験も浅く、年齢も若い私が、年上のパートさんたちを引っ張っていくなんて、うまくいくはずがありません。気がつけば、がんばるほどに空回りし、「あの子は仕事もできないのに、偉そうに指示だけしてくる」と思われ、距離を取られてしまいました。
私としては敬語も使っていましたし、「社員らしくしろ」と言われたとおりに、誠実にやっていたつもりでした。仕事仲間に対する姿勢として、本当に必要だったのは、指示や命令ではなく「お願い」や「依頼」をしながらチームを動かすこと。「自分一人で動かそうとすること」ではなく、「みんなで協力すること」でした。
“リーダーらしく見せる”ことではなく、“自分らしく関わる”ことのほうがずっと大切なのだと、身をもって学んだ出来事でした。
1.自分を整える 〜リーダーシップは内側から始まる〜
どんなに優れたスキルを持っていても、心が乱れているリーダーに、人はついてきません。
焦り、苛立ち、不安…これらを感じること自体は自然なことですが、その状態を放置すると周囲への関わり方がぎこちなくなります。リーダーの状態が影響し、チーム全体が落ち着きを失ってしまうのです。
だからこそ、リーダーシップの第一歩は「自分を整えること」。整えるとは、感情を押し殺すことではなく、「今の自分の状態に気づき、受け入れること」です。「焦っているな」「少し余裕がないな」と気づけた時点で、もう整える準備は始まっています。
たとえば、深呼吸をしてから話す。気持ちがざわつくときは、5分間席を立ってお茶を入れる。夜はスマホを置いて、静かにお風呂に浸かる。こうした小さな習慣の積み重ねが、自分を穏やかに保つ力になります。
自己管理ができて、整っている人の周りには、安心感が生まれます。人は完璧な人よりも、落ち着いた人に信頼を寄せるのです。自分の状態に気づき、心を整えられる人が、人の気持ちも受け止められるようになります。
2.よく見る 〜人と状況を“観察する力”がリーダーをつくる〜
「リーダーには決断力が必要だ」とよく言われますが、実際の現場でより大切なのは“観察力”です。部下の表情、チームの空気、会議中の沈黙。そうした小さな変化を見逃さずにいられれば、一番チームに良い決断がしやすくなります。
「見る」というのは、ただ目に映すことではなく、「相手の中で何が起きているのか」を感じ取ろうとする姿勢のこと。あの人、今日は少し元気がないな。最近、表情に疲れが見える。そうしたサインを見抜ける人は、問題が大きくなる前に手を差し伸べることができます。
観察とは、相手への関心の表れです。「あなたのことをちゃんと見ている」というまなざしが、部下に安心を与えます。見る力を育てることは、相手を大切に扱う力を育てることなのです。
日頃の部下の様子をよく見ずに、リーダーシップをとることはできるはずがありません。

3.聴く 〜相手の“心の声”を受け止める〜
見ることができるようになったら、次は「聴く」こと。
多くの上司が“伝える力”をリーダーシップだと考えますが、本当に人を動かすのは“聴く力”です。
話を聴いているつもりでも、つい「でもね」「それは違うんじゃない?」と口を挟んでしまうことがあります。けれど、それは相手の話を聴いているようで、実はあなたの物差しで“評価”しているのです。
聴くとは、相手の中にある“気持ち”を受け止めること。言葉の正しさではなく、感情の奥にある思いに耳を傾けることです。「そう感じていたんだね」と一度受け止めるだけで、相手は「理解されている」と感じ、信頼が生まれます。
聴くことは、相手を変えるための行動ではありません。理解しようとする姿勢そのものが、相手の心を開きます。そして、人の話を聴けるようになるほど、自分の感情にも耳を傾けられるようになります。
4.感謝と承認を伝える 〜“見ているよ”を言葉にする〜
経験が浅いリーダーほど、「もっと厳しくしなければ」「結果を出さなければ」と気負いがちです。しかしし、チームを動かす力は叱責ではなく、“感謝”と“承認”にあります。
感謝の言葉、「ありがとう」「助かりました」こういった一言が人を大きく動かします。感謝の言葉は、相手の努力や配慮に気づいた人にしか言えません。つまり、“よく見ている人”ほど、感謝の言葉が増えるのです。
承認とは、結果だけでなく、プロセスを褒める・認めることを含みます。「前よりも丁寧に仕上げてくれたね」「忙しい中でサポートしてくれて助かったよ」。こうした声かけが、相手の自己承認力を育てます。
リーダーの役割は、「できていないところを探すこと」ではなく、「できていることに焦点を当てること」。光を当てられた人は、自ら成長しようとするのです。
5.信じる 〜相手の可能性を“先に見る”〜
最後にお伝えしたいのは、「信じる力」です。あなたは、チームのメンバーを信じていますか。
仕事を任せるときに、「あの人にはできないだろうな」「自分がやったほうが早い」
そんな風に感じることもあるかもしれません。
しかし、チーム力を高めていくうえで大事なことは、“相手の可能性を見る”ことです。
「きっとできる」と思って任せることで、相手の中にも「自分を信じてみようかな」という力が生まれます。もしも、結果が伴わない場合は、上司がフォローすればいいだけのことです。
自分を信じられる人ほど、他者を信じることができます。仕事を任された部下は、必ず成長していきます。
ご自身の過去を振り返ってみてください。あなた自身もそうだったのでは、ないでしょうか。
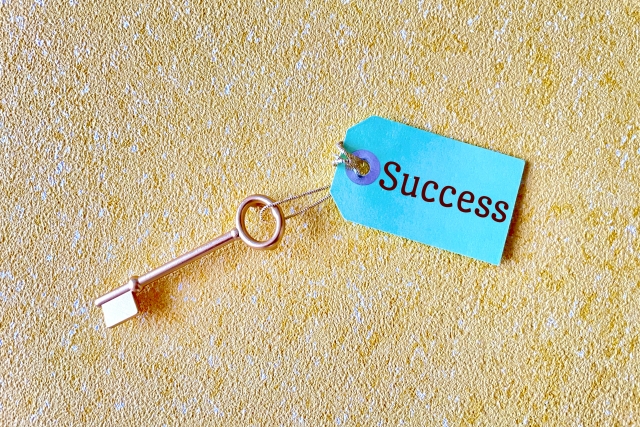
経験ゼロのリーダーほど、信頼をつくるチャンスがある
リーダーシップとは、“心を動かす力”です。その力は、経験ではなく、日々の姿勢の中にあります。
| リーダーシップの5つの行動 | 意味 |
|---|---|
| 1. 自分を整える | 安定感と信頼を生む土台をつくる |
| 2. よく見る | 相手への関心を示し、違和感に気づく |
| 3. 聴く | 相手を理解し、安心感を与える |
| 4. 感謝と承認を伝える | モチベーションを引き出す |
| 5. 信じる | 相手の可能性を育て、成長を促す |
どれも特別なスキルではなく、誰でも今日から始められる行動です。
そして、この5つはすべて、あなた自身を信じる力、「自己承認力」とつながっています。自分の状態を認め、整え、相手を受け入れ、信じる。この循環が起きることで、チームは自走するようになります。
まとめ:リーダーシップは、誰の中にも眠っている
いかがでしたでしょうか。
経験がなくても、役職がなくても、あなたの中には“リーダーシップの種”がすでにあります。その種を育てるのは、特別な経験ではなく、日々の「整える・見る・聴く・承認する・信じる」という行動です。
リーダーシップとは、人の心を動かし、関係をつくる力。そして、それを支えるのが“自分を整える力”です。経験ゼロのリーダーだからこそ、つくることができる関係性があります。
焦らず、一歩ずつ。まずは今日、「自分を整える」ことから始めてみましょう。
その一歩が、あなた自身を成長させ、誰かの信頼を生む最初のリーダーシップになるはずです。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

