こんにちは!自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
あなたは普段、上司からどんな風に呼ばれていますか?
もしかしたら、職場で「上司から名前を呼び捨てにされること」に、違和感を抱いたご経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
「え?いきなり呼び捨て?」 「なんだか下に見られている気がする…」
そんなふうに、胸の中にモヤモヤが生まれる瞬間があるかもしれません。
しかし、ここで考えてみましょう。
【呼び捨てされること】が嫌なのでしょうか?
【あの上司に呼び捨てされること】が嫌なのでしょうか?
実はこの違いがとても大切なヒントになります。
このコラムでは、呼び捨てに違和感を抱く理由と、呼び捨てする上司の心理、そして違和感への向き合い方を解説します!
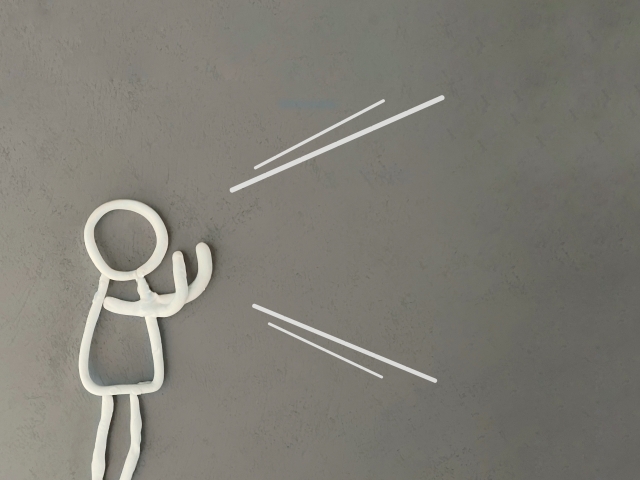
呼び捨てされることへの違和感の正体
まずは、あなたが感じる「違和感」の正体についてです。
なぜあなたは「上司から呼び捨てされること」に違和感を覚えるのでしょう。
たとえば、あなたがある日社長から呼び捨てにされたときに「名前を覚えてもらえた!」「距離が縮んだ気がしてなんか嬉しい」と思ったのに、直属の上司である課長から呼び捨てにされたら「なんかイラっとする」「見下されてる気がする」と感じる。
こうした感覚の違いは、「呼び捨て」という行為そのものが失礼かどうかよりも、 “その人との関係性”や“普段の接し方”によって受け取り方が変わるということを示しています。
つまり「呼び捨て」という行為がOKかNGかは一旦置いておいて、自分が相手のことをどう感じているのか?に注目をすることをおすすめします。
ここで、ご自身にひとつ問いかけてみてください。
「私はこの上司を信頼できているだろうか?」
「この上司の仕事ぶりを尊敬できているだろうか?」
「この上司から、普段どんなふうに扱われていると感じているか?」
実は、呼び方に対する印象は、こうした“心の中の評価”によって大きく左右されます。 つまり、呼び捨てにされたからモヤモヤするのではなく、 “その人に敬意を持てていないからこそ”モヤモヤする場合もあるのです。
そう考えると、違和感の正体は相手との信頼関係にあるのかもしれません。
呼び捨てに隠れた上司の心理
ここからは、上司の心理に注目をしていきましょう。そもそも上司はなぜ部下を呼び捨てにするのでしょうか?
① 親しみを込めて呼んでいる
部下と距離を縮めたい、フレンドリーな関係を築きたいという思いから、あえてラフな呼び方を選んでいるケースです。
あなたも、友達と仲良くなりたいときに、自然とあだ名をつけたり、名前を短く呼んだりした経験はありませんか?
呼び方をカジュアルにすることで、心理的な距離を縮めようとしているのです。
ただし、これは「親しみを込めているつもり」なだけで、相手がどう感じるかまでは考えていないこともあります。
② 上下関係の強調
一方で、親しみとは逆に、上下関係を強く意識するケースもあります。
「自分の方が上の立場だ」という意識が強く、権威を示すために呼び捨てを使っているケースです。
無意識のうちに上下関係を強調し、「部下は従うもの」という価値観が表れている場合もあります。
特に、自分が厳しい上司に育てられた経験を持っている人は、そのやり方が正しいと信じて疑わない傾向もあります。
呼び方一つに、立場の優劣を刷り込むような意図が含まれている場合もあるのです。
自分が上司になった途端に、年上の方たちを呼び捨てにしたり、タメ口や命令口調になった管理職を何人か知っていますが、私は人として尊敬はできないなと思います。
③ 無意識の癖や社風
特別な意図があるわけではなく、「部下は呼び捨てするもの」「昔からそうしてきた」「みんなもそうしている」といった“慣習”や“社風”からきているケースです。
年功序列が強かった時代や、「上司=偉い人」という空気が色濃かった世代では、呼び捨てが当たり前だったこともあります。自分も上司に呼び捨てにされてきたので、同じことを部下にもするのです。
実際、私自身も上司からは大概呼び捨てにされてきましたが、全く不快に感じたことはありません。それは、社風がそうだったのかもしれませんし、信頼関係が構築されていたからだとも思います。

呼び捨てにされたいと感じる人もいる
ここでもうひとつ、大切な価値観をご紹介します。
それは、「上司や先輩には呼び捨てにしてほしい」という思いを持つ方もいるということです。
この価値観の背景には、
- 自分を後輩・部下として近い存在と感じてほしい
- 可愛がってほしい、気にかけてほしい
- 名前を呼び捨てにされることで“認められている”と感じる
といった、愛情を感じたい・距離を縮めたいという気持ちが隠れているかもしれません。
つまり、呼び捨てがすべてNGというわけではなく、人によっては「関係性の温度」を表すこともあるということなのです。
呼び捨てはもう主流ではない
ここではっきりお伝えしておきたいのが、良い悪いではなく、現代のビジネス現場では「〜さん付け」が主流ということです。相手への敬意を示すうえで「名前+さん」で呼ぶことが社会人として基本のマナーとなっています。
どの役職も年齢も関係なく、「~さん」と呼び合うことをルール化している企業様もあります。A部長・B課長などの役職は、対外的に付ければいいので、それはそれで楽かもしれません。
社風や昔からの癖の場合は、なかなか呼び方を変えることは難しいですが、期初や新人さんが入ってきたタイミングなど全員が取り組みやすいときに試してみるのもいいかと思います。

どうしても「呼び捨てされたくない」なら対策を考えてみよう
呼び捨てに違和感を覚えながらも、「我慢すべきかな…」と悩んでいる方もいるかもしれません。
そんなときには、無理に耐え続けるのではなく、自分から提案してみるのもひとつの方法です。
たとえば・・・
「提案が1つあります。チームの中のお互いの呼び方についてです。今の時代の流れに乗って、部下もアルバイトさんもうちのチームは全員“さん付け”で統一するのはどうでしょうか?」
上司に対して「自分を呼び捨てしないでくれ」とは言い出しにくいもの。
ですので、このように全体の働きやすさや公平性の視点から伝えると、角が立たず受け入れられやすくなります。
そして、この提案するご自身が、どなたに対しても“~さん”と敬意を払う。その姿勢を貫けば、きっと周りの方にもその空気が伝わります。
まとめ:大切なのは、呼び方ではなく関わり方
呼び捨てがOKかNGか。 人それぞれ感じ方が異なりますので、白黒つけられるものではありません。
しかし、ご自身が上司から呼び捨てされることに対して、強く反応してしまうとき。そんなときには、自分のストレス状況と自己承認力に注目をなさってみてください。
自己承認力が高まると、
- 自分の感情に敏感、素直になれる
- 他者の言葉に過剰に傷つかなくなる
- 伝えるべきことを落ち着いて伝えられる
違和感を感じることに対して、対処ができるようになっていきます。
「呼び捨てされて嫌だと感じる私は神経質?」そうではありません。
「そう感じた自分」に気づき、その背景を理解し、必要に応じて相手と対話をする。
それが、ビジネスパーソンの心の整え方。
どんな呼び方であれ、相手への敬意を大切にしながら、関係性を育むことが第一です。
あなたのその気づきが、より良い人間関係のスタートになるかもしれません。
そして、自分の心を整えることは、相手との関係性をより豊かに育む力にもなります。
あなた自身の心の動きに優しく寄り添いながら、日々を進んでいきましょう。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

