こんにちは!自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
「部下に仕事を頼んだのに、すっかり忘れられていた」
「期日を過ぎてから慌てて提出される」
「やりかけのタスクが山積みで、優先順位がバラバラ」
…こんな場面、ありませんか?
実はこれらは、タスク管理が苦手な部下に共通するサインです。
上司にとって、タスク管理ができていないのは大きな悩みですよね。
そこでつい言ってしまいがちな言葉があります。
「ちゃんと期限守って!」
「最優先からやって!」
…私も身に覚えがありますが、実はこれでは指導になっていないのです。
タスク管理が苦手な部下に必要なのは、「仕組みとサポート」。
部下がやりやすい方法を一緒に探す姿勢こそが、上司としての信頼を築く大事なステップです。
実は、私自身も元々はタスク管理が得意ではありません。
そんな自分のことをよく知っているので、朝は家を出る3時間前に目覚ましをセットします。
普段は、腕時計を15分以上早めて生活していますし、締切よりずいぶん前に「内部締切」を設定したり。
今日やることは全部書き出して、デスクトップに付箋アプリを貼りつけて管理しています。
いろいろ試した末に付箋アプリが一番しっくりきたのです。
そんな私だからこそ、タスク管理が苦手な人の気持ちはよくわかります。
「性格や能力の問題」と片付けるのは早すぎます。改善はできるからです。
そこで今回は、部下のタスク管理を助ける7つの業務管理法を、自己承認力の観点も交えてご紹介します。
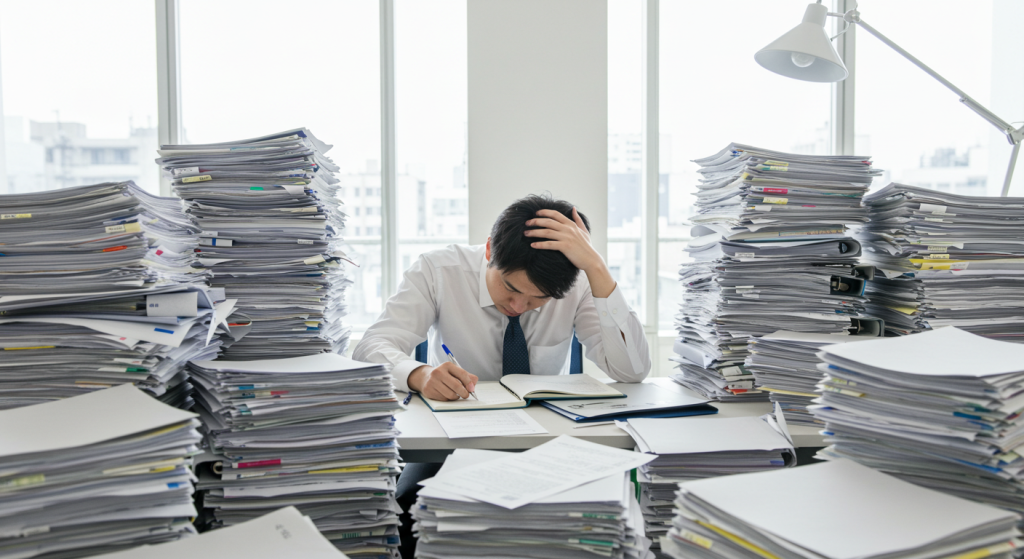
1. 仕事を「見える化」する
口頭だけの指示は忘れやすく、認識の食い違いも起きやすいものです。
必ずタスクを見える化しましょう。
- メールやチャットで文字に残す
- 付箋やホワイトボードで一覧化する
- タスク管理アプリを活用する
ポイントは「誰が・いつまでに・何を」を明確にすること。
特に苦手な部下には、1タスク=1付箋で管理するのがおすすめです。
一つ終わったら、項目が減る達成感も味わうことが出来ます。
2. 優先順位を一緒に決める
タスクを抱え込み、パンクしている部下は「何から手をつければいいのか」が整理できていないことが多いです。優先順位のつけ方は、伝えているでしょうか。どのように段取りするかは伝えているでしょうか。
教わっていなかったら、出来ないのも当然。
上司が一緒に優先順位を決める時間をとるだけで、あっという間に整理されます。
この時間は、「部下が抱える業務量」を確認することもできるので、上司にもメリットがあります。
「これは今日中に」「これは今週でOK」など、赤・黄・青の3色で仕分けするのも効果的です。
優先順位を一緒に確認することは、チーム内の業務バランスを調整するのにも最適です。
3. タスクを小さな単位に分ける
「企画書を作っておいて」では、タスク管理が苦手な部下にとっては大きすぎる指示です。
✔︎ 情報収集
✔︎ アウトライン作成
✔︎ 下書き
✔︎ 修正
✔︎ 提出
「企画書を〇月×日までに仕上げてほしいんだ。まずは、情報収集を水曜日までにやってもらえる?」
このように小さく分けてから指示を出すことで、行動に移しやすくなります。「できた!」という小さな成功体験が積み重なると、自己承認力(やればできる!という感覚)も高まります。
4. 前倒しの締切を設ける
私自身の経験からも、前倒しの締切を設定することが効果的だと実感しています。
例えば、資料づくりでしたら前倒しの締切=3日前を上司に提出する。ミスを指摘されても、3日あれば修正が可能ですよね。余裕を持つことで焦りやミスが減り、結果的に精度が上がります。
タスク管理が苦手な人ほど、「ギリギリ」に設定していることが多いです。公式な締切ではなく、自分自身の締切を別で設定しておくことがおすすめです。
こういった心の余裕を持たせる仕組みをつくるのも上司の役目です。

5. 定期的に進捗をチェックする
「指示を出したから大丈夫だろう」と放置すると、タスク管理が苦手な部下は迷走します。
かといって細かく詰めすぎるとプレッシャーで動けなくなることも。
おすすめは、軽い進捗チェックを習慣化することです。
- 毎朝5分で「今日のタスク」を確認
- 週1回の進捗ミーティング
- チャットで「今どんな感じ?」と気軽に声をかける
進捗を報告する習慣をつけておきましょう。お互いに心理的にも安心感が生まれます。
6. 成果物のイメージを共有する
タスク管理ができない原因の一つに、「ゴールが曖昧」というケースがあります。
「どのレベルまで仕上げればいいのか」「誰が見るものなのか」を上司が具体的に伝えるだけで、部下の迷いがなくなるかもしれません。
ある企業のケースをご紹介します。上司が部下に対して、「部内の清掃リーダー」に任命しました。
ところが、数か月経っても進んでいる気配がありません。
これは、「清掃リーダー」の説明が曖昧で、部下に伝わっていなかったことが原因でした。
上司:「チームメイトに呼びかけて清掃活動をほしかった」
部下:「清掃時間に他の人より積極的にやるようにしていた」
明確なゴールを共有していないことで、仕事の質が下がることはよくあります。
期待値のすり合わせは、タスク漏れや手戻りを大幅に減らしますので、確認してみましょう。
7. タイプに合った仕組みを探す
部下によって「つまずきポイント」は違います。部下がタスク管理ができない、その理由は何かを把握していますか?
- 忘れっぽくて、指示が整理できていない
→ 業務の洗い出し、リマインドを強化 - 時間管理が苦手で間に合わない
→ 前倒しスケジュールを組む - 完璧主義でこだわって時間がかかる
→ 60%で一度確認をする - 得意・不得意が極端で、苦手な業務が大幅に遅れる
→グループやペア作業、役割分担で得意分野を任せる
実際に私の部下でも、性格に合った方法を試したら大きく改善した例がありました。
「時間管理が苦手なんです…」というので、私の時間管理の方法を試してもらったのです。
相手の特性に合わせた仕組みを試していきましょう。
まとめ:仕組みづくりは「部下育成のひとつ」
いかがでしたでしょうか。
部下がタスク管理ができないと、上司としてイライラしてしまうのは自然なことです。
しかし、そこで「できないから仕方ない」と諦めるのは早い。
✔︎ 見える化する
✔︎ 優先順位を一緒に決める
✔︎ タスクを小さく分ける
✔︎ 内部締切を設ける
✔︎ 定期的に進捗をチェックする
✔︎ 成果物のイメージを共有する
✔︎ タイプに合った仕組みを探す
これらを一緒に試すことが、部下の成長を助けることに繋がります。
タスク管理の仕組みづくりは、単なる効率化ではなく「部下育成」そのもの。
計画通りに仕事が進まないときの、上司自身の感情コントロールも試されるところです。
明日からできる小さな一歩は、「まず一緒に話し合って試してみる」こと。
部下のスタイルに合わせて、仕組みをつくり、落とし込んでいく。
一緒に挑戦していきましょう!
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

