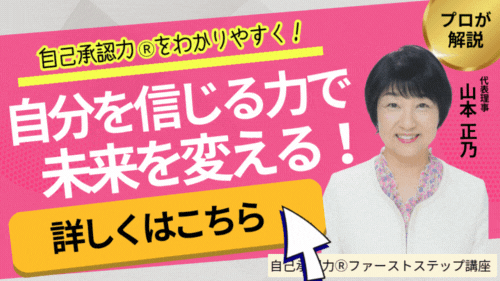いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
自己承認力コンサルタント協会 代表理事の山本まさのです。
「やればできる!」——よく聞く励ましの言葉ですが、これは単なる精神論ではなく、心理学的に裏付けのある「力」なのです。
当協会(一般社団法人自己承認力コンサルタント協会)では、「自分を認め、信じて前に進む力=自己承認力Ⓡ」を提唱し、自己肯定感・自己効力感・スキルの3つを柱に実践プログラムを行っています。
本記事では、その中核要素の一つである「自己効力感」に焦点を当て、理論と実例を交えて、「やればできる」を実感に変える方法をお伝えします。
「やればできる!」を本当の力に変える「自己効力感」とは?
自己承認力Ⓡは、「自分を認め、信じて前に進めるチカラ」です。
この力を構成する3つの要素のうち、「自己効力感」とは「未来の自分の行動や成長を信じられる力」のこと。
- 「私ならできる」
- 「まだ無理でも、やれば伸びる」
- 「チャレンジしてみたい!」
こうした前向きな信念が、行動を生み、結果につながります。逆に「無理」「できない」と思ってしまうと、チャンスを逃したり、すぐに諦めてしまったりするのです。
この“信じる力”「自己効力感」こそが、自己承認力を根底から支えています。
自己効力感とパーソナリティとの関係
心理学におけるビッグファイブ(外向性、神経症傾向、開放性、協調性、誠実性)のうち、開放性と誠実性が高い人は、自己効力感が高い傾向があります。
実例として、クリエイティブな発想を生かす小規模スタートアップで働くAさんのケース。彼女は自発的に新プロジェクトを提案し、成功体験を重ねることで「自分なら新しい分野でもやれる」という自己効力感を得ました。
一方で、他人からの評価を強く気にする「神経症傾向」が高い人は、他者の反応に左右されやすく、成功を認めづらく、失敗で自己効力感を失う場合があります。
自己効力感とメンタルヘルスとの相関性
研究では、自己効力感の高さは心身の健康と密接に関係していることが示されています。
うつ病治療に自己効力感を利用した認知行動療法(CBT)では、患者が小さな成功を積み重ねることで「できた!」という感覚を実感し、抑うつ傾向が軽減されるという報告があります。
実際、職場で大きな失敗をしたBさんの場合。最初は落ち込みましたが、上司の「小さなタスクから始めよう」というアドバイスと達成体験により自己効力感が回復。やがて彼は再び本来の力を出し、プロジェクトを成功させました。
自己効力感の心理学的背景
アルバート・バンデューラの社会的認知理論
1977年、バンデューラは「社会的認知理論」を提唱し、1977年、心理学者バンデューラは「社会的認知理論」を提唱し、自己効力感という概念を体系化しました。
行動を「観察」「認知」「実行」「再評価」のループで捉えました。実際、彼が行った「ボボ人形実験」では、他者の行動を観察するだけで子どもの行動傾向が変わることが明らかにされました。これは代理体験による学びの一例です。
また、成人を対象とした研究では、自己効力感の高い人は、同じ課題でも挑戦意欲が強く、実際の成果も高いことが示されています。例えば、新しい仕事に直面した時、自己効力感が高い人は「この仕事は習得できる」と思う一方、低い人は「高すぎる目標だ」と感じやすい傾向がありました。
彼の研究では、人が自らの行動結果を「観察→認知→実行→再評価」する中で、「自分にはできる」と感じたとき、行動が継続し成果につながるとされています。
自己成就予言と現実の変化
当協会でも伝えている「自己成就予言」や「ピグマリオン効果」によって、「できると思えば現実も変わる」ことが多くの事例で確認されています。
受講者の中には、「『私は無理』と口にする癖をやめただけで、チャレンジできるようになった」と語る方も多くいます。
「やればできる」を支える4つの源
バンデューラは、自己効力感の形成に必要な4つの要素を示しました。当協会の講座でも実践的に活用しています。
成功体験(Mastery Experiences)
例:資料作成を一度成功させたことで、「次はもっと難しい企画書もできる」と信じられるようになった会社員Cさん。
代理体験(Vicarious Experiences)
例:同じ職場の同僚が苦手な顧客対応を克服したのを見て、「自分にもできるかもしれない」と思えた営業職Dさん。
言語的説得(Verbal Persuasion)
例:「君に任せてよかったよ」の一言が、ある女性管理職の自己効力感を押し上げ、プロジェクトの成功を導いた実話。
生理的・情動的反応(Physiological States)
例:講座中に教わった「深呼吸+自己対話」で緊張が和らぎ、「自分はやれる」と確信できた主婦受講者Eさん。
実践的アプローチ ~自己効力感をどう育てるか?
認知行動療法(CBT)の応用
- 認知再構成:「失敗するかも」→「うまくいかなくても学びになる」
- 行動ステップの分解:「すべて任される」ではなく「まず目次から」
- 振り返り習慣:「できたこと日記」「自己評価ジャーナル」など
教育や職場での支援策
- スキャフォールディング:徐々に支援を減らし、自律的挑戦を促す
- ピアモデルング:他者の成功体験を見せる
- 言語的承認:「頑張ってるね」「そのやり方いいね」と伝えることで、信念が育つ
セルフモニタリングと習慣づくり
- 毎晩「今日の小さな成功」を書く
- SNSやサークルで成果報告を共有
- 自己労いの言葉を自分にかける(例:「今日もよくやったよね」)
自己効力感が育つとどう変わるか?
- ✔ 挑戦への不安が減る
- ✔ 行動が続く
- ✔ 成果が出る
- ✔ 自己肯定感も自然に高まる
- ✔ 他人の目に振り回されなくなる
当協会の受講生の声にも、「仕事がうまくいっただけでなく、人間関係まで変わった」という報告が多数寄せられています。
まとめ:自分を信じることが、すべての始まり
自己効力感は、自己承認力を育てるために欠かせない「未来を信じる力」です。
自己肯定感(今の自分を受け入れる)
+
自己効力感(未来の自分に期待できる)
+
スキル(実行する力)
この3つが合わさると、自己承認力が高まり、「やればできる」が単なる希望ではなく、確信になります。
たとえ失敗しても、心の中に「自分なら、まだできる」がある限り、人は立ち上がれるのです。「やればできる」は、あなたの中にすでにある力です。
今ここから、小さな一歩を踏み出してみましょう。あなた自身が「できる人」になる、その旅が始まります。
今日から、あなたの「やればできる」を実感する一歩を踏み出してみませんか?