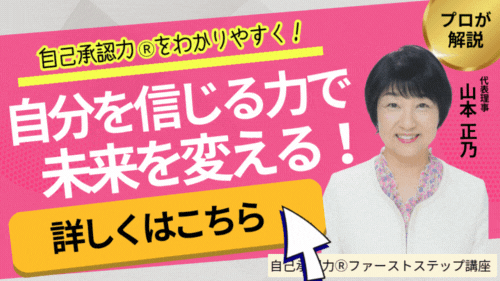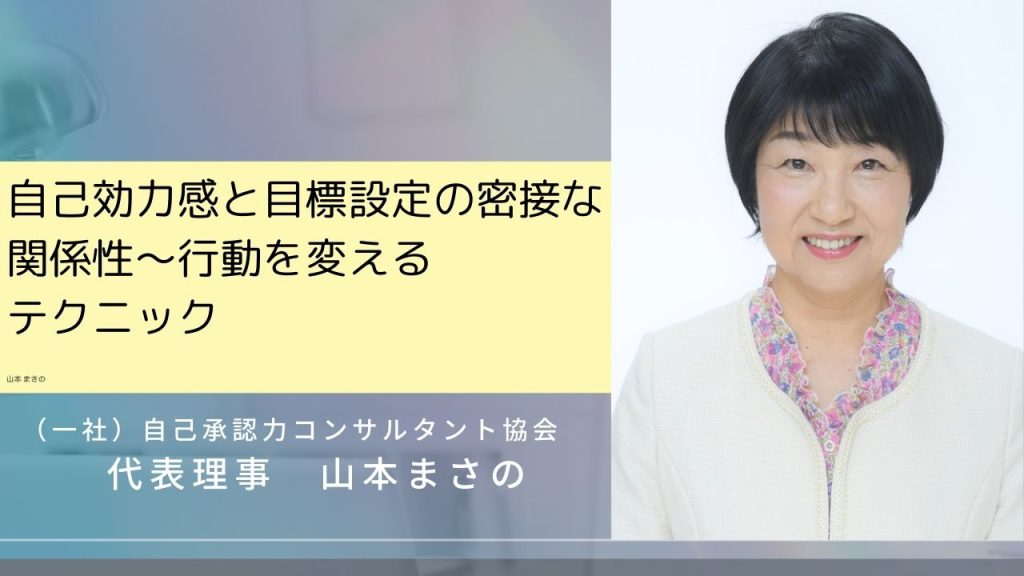
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。自己承認力コンサルタント協会 代表理事の山本まさのです。
「やろうと思っても続かない」「目標を立てても挫折してしまう」
そんな経験はありませんか?実はその背景には、“自己効力感”という心理的な要素が大きく関係しています。
自己効力感とは、「自分ならできる」という自信や確信の感覚です。心理学者バンデューラによって提唱されました。
この感覚が高まると、行動する力が自然と湧き、目標を現実のものに変えていけるようになります。逆に、自己効力感が低いと、どれだけ素晴らしい目標を立てても途中であきらめてしまいやすくなります。
本コラムでは、自己効力感と目標設定の関係性を分かりやすく解説しながら、
実際に行動を変えるためのテクニックや、今日から使える習慣づくりのヒントをご紹介します。
あなたの「変わりたい」を実現する一歩に、ぜひお役立てください。
自己効力感と目標設定の密接な関係性
自己効力感が高いと目標達成しやすくなる理由
自己効力感が高い人は、目標に対して前向きに行動できる力を持っています。
たとえば、同じ「毎朝ランニングする」という目標でも、自己効力感がある人は「少しずつならできそう」と感じて実行に移しやすくなります。逆に、自己効力感が低いと「どうせ無理」と感じてしまい、挑戦する前に諦めてしまうのです。
自己効力感が高いと起こる変化
- 行動へのハードルが下がる:「とりあえずやってみよう」と思える
- 継続力が上がる:「多少うまくいかなくても続けよう」と前向きに取り組む
- 達成感が積み重なる:小さな成功が次のモチベーションにつながる
つまり、自己効力感は「やる気」や「意志の強さ」よりも、行動の継続性を高める鍵なのです。目標達成を目指すなら、まずは「自分ならできるかも」という心の状態を整えることが、成功への第一歩になります。
「できるかも」と思える目標の立て方
自己効力感を高めるためには、最初から高すぎる目標を設定するのではなく、「できるかも」と思える目標を立てることが大切です。
目標が現実離れしていると、自信を失いやすく、達成感も得られにくくなってしまいます。
ポイントは「小さな達成感を得られるか」
たとえば、「毎日2時間運動する」という目標よりも、
「1日10分ストレッチをする」のようなハードルの低い目標から始めることで、「自分にもできた」という感覚を得やすくなります。
この「できた感」が自己効力感を少しずつ育て、行動の継続につながっていきます。
「できるかも」目標の作り方3ステップ
- 現在の自分の状況を正直に見る
→ 無理なくこなせる行動レベルを見極める - 目標を「具体的」にする
→「毎日頑張る」ではなく「朝7時に10分だけ散歩」のように明確に - 期限をつけて、短期で区切る
→「まずは3日間続ける」など小さなスパンで成功体験を重ねる
「続けられる目標」が、自己効力感を育てる最大の近道です。
最初は控えめでも構いません。大事なのは、「できるかも」が「できた!」に変わるプロセスを作ることなのです。
成功体験が心を変えるメカニズム
人は「成功した経験」を通して、自信を深め、行動力を強くしていきます。
これはまさに、自己効力感が育つ最も強力な方法のひとつです。
成功体験がもたらすのは、単なる結果ではありません。
「自分はやればできる」という感覚が芽生えることで、次の行動にもポジティブな影響を与えるのです。
成功体験が与える心理的な変化
- 自分の能力に対する評価が変わる
→「ダメかも」から「案外いけるかも」へ - 次の挑戦に対する抵抗が減る
→行動のハードルが下がり、動き出しやすくなる - 自分自身を信じる気持ちが強まる
→不安や失敗への恐れが軽減される
成功体験は小さくてもOK!
大切なのは、「結果の大きさ」よりも達成したという感覚です。
「3日間だけ早起きできた」「今日は予定通り行動できた」など、小さなことでも“できた”という実感が積み重なれば、それが次の行動の原動力になります。
つまり、成功体験は自己効力感を育てる「肥料」のようなもの。
こまめに水をやるように、小さな成功を繰り返すことで、あなたの行動力は着実に伸びていきます。
挫折しない目標設定のテクニック
SMARTゴールでぶれない目標を作る
目標を立てても途中で挫折してしまう…そんな悩みを防ぐには、「SMART」というフレームワークを活用した目標設定が効果的です。心理学者ロックによって提唱された理論です。
SMARTとは、目標を具体的に・達成可能にするための5つの条件の頭文字をとったものです。
SMARTゴールとは?
| 項目 | 内容 | 例 |
| S(Specific) | 具体的である | 毎朝6時に起きてストレッチ |
| M(Measurable) | 測定可能である | 10分間ストレッチをする |
| A(Achievable) | 達成可能である | 無理のない時間と内容 |
| R(Relevant) | 目標と関連している | 健康習慣の一環としてのストレッチ |
| T(Time-bound) | 期限がある | まずは1週間続ける |
このように、SMARTゴールを使うと「ただ頑張る」から「何をどう頑張るのか」が明確になり、自己効力感も高まりやすくなります。
自分が何に向かって、どんな行動をすればいいのかがクリアになることで、行動に迷いがなくなり、継続もしやすくなります。
目標が“ぶれない”ことで、心も行動も安定し、着実に前進していけるのです。
小さな達成で自信を育てる方法
「目標が達成できた!」という成功体験は、自己効力感を大きく育てる栄養になります。
特に、小さな目標の達成は、自信を積み重ねるために非常に効果的です。
小さな達成がもたらす3つの効果
- 「やればできる」という感覚が得られる
→ 結果が小さくても、「行動した」という事実が自信になる - 継続の原動力になる
→ 一度でも成功すると、「またやってみよう」と思える - 習慣化しやすくなる
→ 毎日の積み重ねが自己効力感を維持・向上させる
実践のコツ:「ミニゴール」を設定する
- 例1:「1日30分勉強」→「まず5分だけ机に向かう」
- 例2:「1日1記事書く」→「まずタイトルだけ決める」
こうした“超ハードルの低い目標”を設定することで、最初の一歩が踏み出しやすくなります。その「できた!」の実感が、次の行動につながっていくのです。
最初から完璧を目指すのではなく、「できること」から始める。
それが、自己効力感を育てる最も確実な道です。
途中でやめたくなったときの対処法
どんなにやる気があっても、継続の途中で「もう無理かも」と感じる瞬間は誰にでもあります。しかし、その壁をどう乗り越えるかで、自己効力感の強さが変わってきます。
挫折しそうなときに試したい3つの対処法
- 「できていること」に目を向ける
→「昨日はサボったけど、先週は4日できた」など、できたことにフォーカスすることで前向きな気持ちを取り戻せます。 - 目標を“再調整”する
→ 高すぎる目標は一時的に小さく変更してOK。重要なのは「続けること」。 - やらない日を「休息」と捉える
→ サボりではなく、エネルギーをためる“準備期間”と考えることで自己否定を避けられます。
気持ちを切り替える魔法の質問
- 「今日は何が少しでもできそう?」
- 「昨日と同じ状態でも、何か1%違う行動ができないか?」
このような問いかけは、思考を“できる方向”へと向ける助けになります。
途中で止まりそうになったときこそ、自己効力感を高めるチャンスです。
うまくいかないときの工夫こそが、継続の力になっていきます。
自己効力感を高める日々の習慣
毎日できる簡単メンタルトレーニング
自己効力感を高めるには、特別なことをする必要はありません。
むしろ、毎日ちょっとしたことを続けることが、心に大きな変化をもたらします。
すぐに実践できるメンタルトレーニング3選
- 「今日できたこと」を毎日1つ書き出す
→ どんなに小さなことでもOK。「早起きできた」「水をたくさん飲めた」など、自分を認める習慣が大切です。 - 未来の自分に声をかけるイメージワーク
→ 「1週間後の私は目標を続けている」と心の中で声をかけ、達成イメージを強めます。 - 前向きな言葉を口に出す
→ 「自分ならできる」「少しずつでいい」と毎日つぶやくだけでも、思考の方向が変わります。
習慣にするコツ
- 朝や寝る前に“セットでやる”(例:歯磨きと一緒に書き出し)
- スマホのリマインダーを活用する
- 目に見えるところにメッセージカードを置く
こうした小さなメンタルトレーニングを続けることで、自己効力感は少しずつ、でも確実に育っていきます。
「ポジティブな言葉」がもたらす変化
日常の中で何気なく使っている言葉が、自己効力感に大きな影響を与えることをご存じですか?特に、自分自身に対する言葉=**セルフトーク(自己対話)**は、行動や思考のベースを形づくっています。
ネガティブな言葉が自己効力感を下げる
- 「どうせ私には無理」
- 「また失敗するに決まっている」
こうした言葉を繰り返すことで、脳は本当に「自分にはできない」と認識してしまいます。
- 「まだできないけど、少しずつ上達している」
- 「今回はうまくいかなくても、学べたことがある」
- 「私ならできるかもしれない」
このような前向きな言葉を自分にかけることで、行動への意欲と粘り強さが自然と生まれてきます。
言葉を変える=思考を変える
言葉は単なる“音”ではなく、思考を方向づけるスイッチです。
だからこそ、「できる」「進める」「やってみよう」というような、未来につながる言葉を意識して使うことが、自己効力感を高める第一歩になるのです。
自己評価を高めるセルフチェック法
「自分にはできる」と思える感覚=自己効力感を育てるには、自分を正しく評価する習慣がとても大切です。ネガティブに偏った自己評価は、努力しても「足りない」「意味がない」と感じてしまい、継続の妨げになります。
セルフチェックで気づきを得る3つの視点
- できたことに注目する
→ どんなに小さな行動でもOK。「今日はいつもより早く起きた」「話しかけるのをためらわなかった」など、具体的な行動を書き出してみましょう。 - 感情を言葉にする
→ 「今日はやる気が出た理由は?」「落ち込んだのはなぜ?」と、自分の心の動きを観察すると、モチベーションのパターンが見えてきます。 - 昨日の自分と比べる
→ 他人ではなく「過去の自分」と比べることで、成長を実感しやすくなります。
セルフチェックの具体的な方法
- 毎日夜に3行だけ日記を書く
例:「今日できたこと/気分/明日やりたいこと」 - 週1で振り返りシートを使う
→ 「できたこと」「うまくいかなかったこと」「来週の小さな目標」などを記録 - ポジティブな自己コメントを添える
→ 最後に「よく頑張ったね」「少しずつで大丈夫」と自分に優しく声をかけましょう。
自分を責めるのではなく、認める・気づく・整えることが、自己効力感を高めるセルフチェックの本質です。
あなたの成長は、毎日の小さな気づきから始まります。
まとめ
この記事では、「自己効力感と目標設定の関係性」をテーマに、行動を変えるための具体的な考え方や実践方法をご紹介しました。
「やればできる」と思えることが、行動の第一歩。
そして、行動が変われば、未来も変わります。
あなたもぜひ、今日から「できるかも」の気持ちを大切にして、小さな一歩を踏み出してみてください。