こんにちは!自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
「部下との距離感、どう取ったらいいのかわからない…」
「仲良くなりすぎるのも違うと思うし、かといって冷たいとも思われたくない」
そんな風にお感じになったことはありませんか?
管理職として部下と良い関係を築きたい、信頼される存在でいたい。けれど、近づきすぎると甘えられそうだし、距離を取りすぎると話しかけづらい上司になってしまう気がする…。非常に難しいですよね。
友達でも兄弟でもない。師弟関係でも親戚でもない。
“上司と部下のちょうどいい距離感”は、誰にとっても悩ましいテーマです。
今回は、「部下との適切な距離感とは何か?」を一緒に考えてみましょう。自己承認力をベースにした具体的な考え方や、日々のコミュニケーションに活かせるヒントもご紹介いたします。
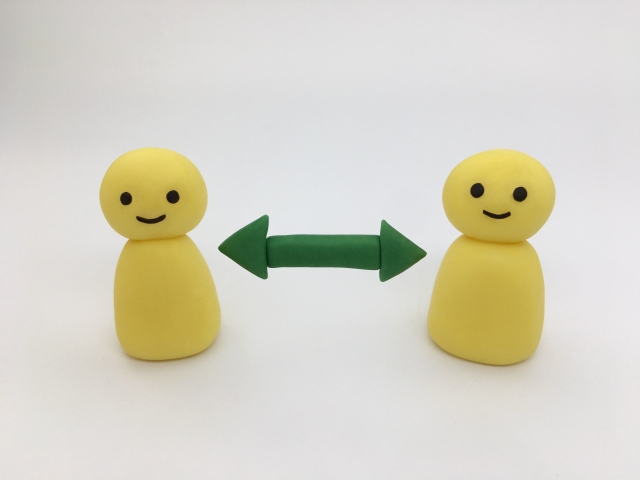
距離感に正解はない。でも、“軸”は必要
結論からお伝えします。部下との距離感に「これが正解!」というものはありません。
だからこそ、“自分なりの軸”を持っていなければ、関係はすぐに崩れます。
あなたはビジネスパーソンとして、
- 部下とどんな関係を築きたいか
- 部下に何を求めるのか
- どんなチームをつくりたいか、どんな成果を出したいか
を自覚し、それを一貫して行動に落とし込めているかどうかが重要です。
「距離感」って具体的にどういうこと?
距離感とは、「どこまで踏み込んでいいか」「どれくらいの頻度で話しかけるか」「どのくらいプライベートを共有するか」といった、心理的な間合いのことを指します。
例えば、人間関係でよくあるすれ違いがこちらです。
- 軽く話しかけたつもりが相手に「詮索された」と受け取られた
- 距離をとっていたら「自分に無関心」と思われていた
- 部下と仲良くなったら「自分がナメられているように感じ始めた」
相手の性格や立場によって“心地よい距離”は違うため、一律のマニュアルでは通用しないのが難しさでもあります。あなたの部下はどんなタイプでしょうか。
こんな風にイメージしてみるといいかもしれません。
お買い物でも食事でも、店員さんと「積極的に話したいタイプ」「程度に距離をとりたいタイプ」「必要最低限の会話で良いタイプ」は人によって異なりますよね。
店員さんとしては、相手を見極めて「サービスに満足してもらうこと」を目指します。
そして、お客様もまた自分が気持ちよくサービスを受け取れるよう「店員さんを尊重すること」を意識するはずです。
こういった距離感をお互いに掴んでこそ、いい関係性が生まれるのではないでしょうか。
上司部下の距離感の前提は「仕事関係」である
ここで一つ、大事な視点をお伝えさせてください。
部下との距離感を考える上で、何よりもまず大前提としておきたいのは「私たちは仕事関係者である」という事実です。
仕事という“共通の目的”があって、そこに役割として存在している関係です。
だからこそ、最も健全で、理想的な距離感とは「お互いが仕事を通して成長できる関係」だと私は考えています。上司と部下がいくら仲が良くても「仕事の結果」が出せなければチームの意味はないのです。
私自身、これまで何度か転職を経験してきました。新しい環境で多くの人と関わりましたが、仕事が終われば関係も自然に終わっていくことがほとんどです。もちろん、限られた一部の方は今でも連絡を取り合っていますが、本当に稀です。
仕事関係は、あくまでも“期間限定の関係”であることが多い。部署異動・退職したら関係性は薄くなります。だからこそ、「今この仕事を一緒にする間、どう関われるか」が重要なのです。

よくある失敗①:近づきすぎた結果、関係が崩れた
ある上司の方は、入社間もない部下との信頼関係を築こうと、「上下関係ではなくフランクにやっていこう」と、自ら積極的に距離を縮める姿勢を見せていました。
最初は良い雰囲気でしたが、しばらくすると、部下が敬語をやめたり、冗談交じりで反論してくるようになったそうです。
すると、上司側の気持ちに変化が現れます。
「なんだか生意気だな…」
「礼儀がなってないんじゃないか?」
と、もともと自分から歩み寄ったはずなのに、部下の反応にイライラしてしまい、最終的には注意するのも気まずくなって、関係がぎくしゃくしてしまいました。
これは上司自身が「ここまではOK、ここからはNG」という明確な基準(心の境界線)を持たずに接してしまったために起こったズレです。
部下からすると「フランクにいこう」と言ってくれた上司に心を開いただけなのに、急に態度がよそよそしくなって混乱しても仕方ないですよね。
よくある失敗②:遠すぎたことで、部下が孤立した
一方で、もう一つの事例をご紹介します。
別の職場で、部下育成に苦労していた上司がいました。とても仕事熱心な方で、「任せることが信頼だ」と考えていたため、部下に自由にやらせ、自分からはあまり口出ししないスタイルをとっていました。
しかし半年後、その部下が突然退職を申し出ました。理由を聞いても「いろいろあって…」と曖昧なまま。後になって周囲から聞いた話では、
- わからないことを相談しにくい雰囲気だった
- 上司が自分に関心を持っていないように感じた
- 評価されているのかどうかが分からなかった
といった、“見えない壁”に悩んでいたことがわかりました。
上司としては「自由に任せていた」つもりでも、部下にとっては「放置されていた」「孤独だった」という印象になってしまっていたのです。完全にコミュニケーション不足から起きた出来事と言えます。
「適切な距離感」を育てる実践のヒント
ここからは、部下との適切な距離感をとるための実践のヒントをご紹介いたします。
部下との距離が遠い・近すぎるなど、ご自身の問題に合わせて実践をなさってみてください。
1.自分の意図を明確にしておく:行動の“理由づけ”がブレを防ぐ
なんとなくで人間関係を築いていませんか。上司部下は、お互いが成長できる関係がベストです。
「今は自立を促したいから、あえて口を出さない」など、行動の理由を自分の中でクリアにしておくことをおすすめします。そして、その意図を面談などで部下にも共有することが重要です。
2.接触回数を意識的に増やす:安心感は“声かけ”で生まれる
毎日、たとえ短時間でも部下に声をかけていますか。挨拶だけで、そのあとの業務は無言…そんな日々を過ごしていると情報も入ってこなくなります。
「〇〇さん、あの件ありがとう。助かったよ」「あの取引先様、どうだった?」など、ちょっとした声がけをすることが信頼関係を築く第一歩です。
3.小さな“自己開示”をする:壁を壊すのは“ちょっとした本音”
自己開示、というのは自分の情報を相手に話すことです。いきなりプライベートを話す必要はありません。「そういえば私も新人の頃、こんなミスをして…」と、自分の経験や気持ちを少しだけ見せることで、距離を縮めやすくなります。
4.部下のタイプに応じて距離を調整する:一律対応では関係は築けない
部下の普段の様子を観察し、タイプに応じて調整をしてきましょう。
- 自信がない部下:やや近く。声かけを多めに
- 自立心の強い部下:程よく任せて、節目で承認
- 新人:細かく進捗確認をしつつ、期待を伝える
- 中堅:役割を明確にしつつ、フィードバック重視
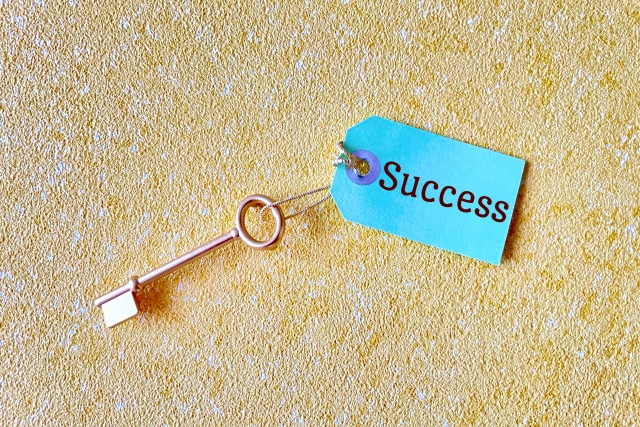
“ちょうどいい距離”を保つためのコツ
距離が近すぎると:
- 注意しづらくなる
- なれ合いになる
- 他の部下からの不信感を招く
距離が遠すぎると:
- 孤独感が強くなる
- 上司への不信が生まれる
- チームの一体感が損なわれる
大切なのは、「今この部下にとって、どんな距離感が安心か?」を見極める“想像力”と、自分自身に軸を持って関わることです。
まとめ:信頼は「尊重×継続」で育つ
いかがでしたでしょうか。人との距離は、「一度決めたら終わり」ではありません。
状況や関係性の変化に応じて、常に“微調整”していくものです。
人によって、今日は「締め切り前だから話しかけられたくない」「プレゼン前で不安だから少し会話したい」など、様々な気分があると思うのです。
その微調整をするスキルを発揮するためには、上司ご自身に「自信」「心の安定」「余裕」があることが重要です。相手をありのまま受け入れて、関係を一歩前に進めていく。
信頼と尊重の気持ちを持って接することが、結果的に「ちょうどいい距離感」につながっていきます。
“信頼される上司”とは、適切な距離を保ち続ける努力を惜しまない人のこと。
“部下とのちょうどいい距離感”は、あなたの意志ある行動から始まります。
一緒に挑戦していきましょう。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

