
こんにちは!自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
あなたは部下育成が得意ですか?
ある程度の経験を積み、部下や後輩が出来ると「人材育成」が仕事の一つになります。
突然「部下を育成しなさい」と言われても、正直どうすればいいのか悩む方も多いと思うのです。
今回は部下育成について改めて深堀りをしていきましょう。
そもそも、育成とは何か?
「育成」という言葉には、単なる「教える」「指導する」という以上に、深い意味があります。
育成とは、
相手の中にある「可能性の種」を信じて、育ちを支援することです。
つまり、
上司が何かを一方的に「与える」のではなく
部下自身が持っている力、意欲、成長の芽を上司が気づき、引き出し、育てていく
このような関わりのことを指します。
ポイントは3つです。
1:「相手の可能性を信じる」こと
人材育成には時間がかかります。すぐに結果が出なくても「この部下は絶対に成長する」と信じることが重要です。この上司の信頼が、部下の自信を育みます。
2:「相手の自立を支える」こと
正解を与えるのではなく、部下自身が答えを見つけられるようにサポートをします。
日常的に業務を見守りながら、相手が必要なときにアドバイスをして背中を押します。
3:「相手と共に成長する」こと
人を育てることは、自分を育てることです。自分自身も常に成長し続ける必要があります。
あの手この手で、部下のサポートをすることで上司と部下が一緒に成長することが出来ます。
部下育成の7つの原則

それでは、具体的にどうすればいいのか?
部下育成に「絶対的な正解」はありませんが、「成果を出す上司の原則」は存在します。
ここからは、管理職として押さえておきたい【7つの原則】をお伝えします。
原則1.「部下を変える」のではなく「部下と一緒に育つ」意識を持つ
上司だからといって、部下を「育て上げなければ」と肩に力が入っていませんか?
部下育成は、教えるだけではうまくいきません。実は教わる力も重要なのです。
「この部下をどう育てようか」ではなく
「この部下と一緒にどんな成長ができるだろうか」と考える。
育成とは一方通行ではなく、双方向の学び合いなのです。
部下が何を考えているのか、どんなことに困っているのか、何が得意なのか。
話を聴きながら、教えてもらいましょう。
原則2.個性と強みを引き出す「承認型フィードバック」をする
部下を育てる際には、「強みを発揮してもらう」視点を持ちましょう。
例えば
「ここがダメだった」というダメ出しではなく
「ここが良かった。さらにこうするともっと良くなる」と伝える。
どうすればいいか?が重要です。
これはフィードバックの定型文として身に着けると良いかもしれません。
似た表現であるあるなのが
× 「〇〇は良かったんだけど、××がダメだった」
これではせっかくの良いところが印象に残りません。結局ダメ出しで終わっています。
部下自身が「自分にはできる力がある」と信じられるようなフィードバックこそ、成長を加速させます。
原則3.「未来志向」で関わる
誰でも失敗をします。今は上司のお立場のあなたも失敗経験を乗り越えてきたはずです。
部下が失敗したとき、責めることはやめましょう。
重要なことは、失敗を再発させないこと、次は成功に近づけることですよね。
「どうしてこんなミスをしたんだ!」と、過去を問い詰めるのではなく
「次はどうする?」と未来に目を向ける。
これが、成果を出す上司の思考の共通点です。
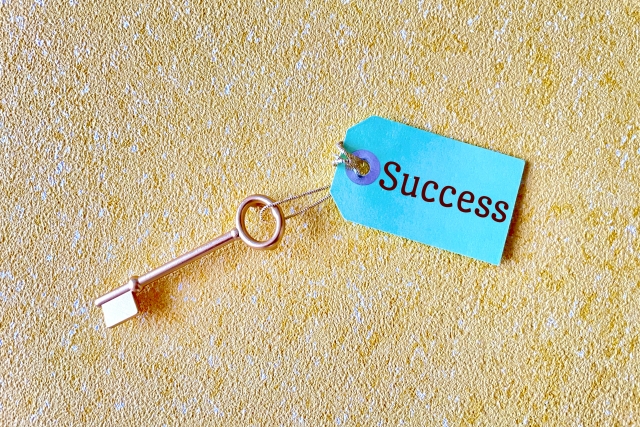
原則4.指示ではなく「目的」を伝える
部下に指示を出すとき、「何をやるか」だけでなく、「なぜやるか」 を伝えていますか?
自分の行動に対して、意味や価値を見出すことで本気で動くことができて、「やりがい」を感じます。
「〇〇をしておいて」ではなく、
「このプロジェクトを成功させるために、〇〇が必要だから頼むね」と伝える。
細かな表現違いと感じるかもしれませんが、この指示の出し方の積み重ねで、部下の仕事への取り組み方が大きく変わります。
原則5.「プロセス」を認める
成果が出たときだけ褒めるのではなく、努力している「過程」を認めることが大事です。
たとえば、
・粘り強く取り組んでいる
・工夫を重ねている
・チームのために動いている
結果ももちろん重要ですが、
「仕事にどんな風に取り組んでいるのか?」その過程や姿勢を承認できる上司は、部下からの信頼が厚くなります。
【具体的な声かけ例】
- 「〇〇さん、あの案件、細かいところまで丁寧に確認していたね。とても助かったよ」
- 「試行錯誤して頑張っていたね。大丈夫、次はさらに良い結果が出るはずだよ」
- 「チーム全体の動きを見ながら行動してくれているのが伝わってきた。ありがとう」
部下が「結果」だけでなく「努力」や「意図」を見てもらえていると感じたとき、部下の自己肯定感が高まり、さらに主体的に動くようになります。
原則6.「安心して失敗できる場」を作る
部下が失敗を恐れて動けない状態になっていませんか。
上司が失敗や出来ていないところを責め続けると、部下は挑戦すること自体が怖くなります。
そして、失敗をした場合に「隠す」という最悪の対応をとってしまうこともあるのです。
部下が「失敗しても大丈夫」と思える環境を作ること。
叱るのではなく、失敗の中から学びを一緒に探すこと。
「挑戦できてよかったじゃないか」「いい経験になったね。そこから何を学んだ?」
そんな声かけが、部下の挑戦心を育てます。
原則7.まず「自分を育てる」
最後に・・・
部下育成で最も重要なのは、上司自身が自分を育て続けることです。
部下を育てることにばかり焦点を当てていませんか。
「成長しない上司のもとでは部下は育ちにくい」
部下育成上手の方は、いつも新しい情報を入れて、自分自身を磨くことに余念がありません。
ご自身にも焦点を当てることを意識していきましょう。
今回は、【自己承認力を高めるためのプチヒント】として
自分自身への声かけをご紹介します。
- 「今日も部下たちに向き合った自分を認めよう。よくやった」
- 「伝え方を迷ったのは、それだけ部下の成長を真剣に考えている証拠だ」
- 「小さな一歩でも、進んでいる。自分が学び続けていることに誇りを持とう」
自分自身にいたわりの言葉をかけながら、成長を続ける。
それが、最も自然で力強い「部下育成」の土台となります。
おわりに:部下育成は自身の成長プロセス
いかがでしたでしょうか。「人を育てる」ということは、本当に難しいことだと思います。
正解がないものですし、日々相手の状況は変わるからです。
部下育成というのは、「部下のため」だけではありません。
上司であるあなたご自身の成長と、チームの未来を作るための大切なプロセスです。
まずは自己承認力を高める言葉を自分にかけながら・・・
一歩ずつ、歩みを前に進めていきましょう。
今、あなたが懸命に蒔いている種は、かならず実る日が来ます。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

