こんにちは!自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
今回は「部下への期待の伝え方」についての特集コラムをお届けします。
「期待している」と伝えたつもりが、なぜか相手に伝わらなかった…
やる気を出してほしくてかけた一言がプレッシャーになってしまった…
そんなご経験はありませんか?
上司から部下への「期待の言葉」は、繊細で影響力の大きいものです。
だからこそ、ほんの少し伝え方を変えるだけで驚くほど相手の反応が変わります。
- なぜ部下に期待を伝えるのか
- 相手に応じたパターン別の伝え方
- ネガティブな評価をする時の伝え方
- 管理職自身のスタンス
今回のコラムは、このような内容も踏まえながら
あなたのチーム力が一段と上がるヒント満載でお届けいたします。
指導で使える「期待の伝え方」は、こちらに詳しく書いております。
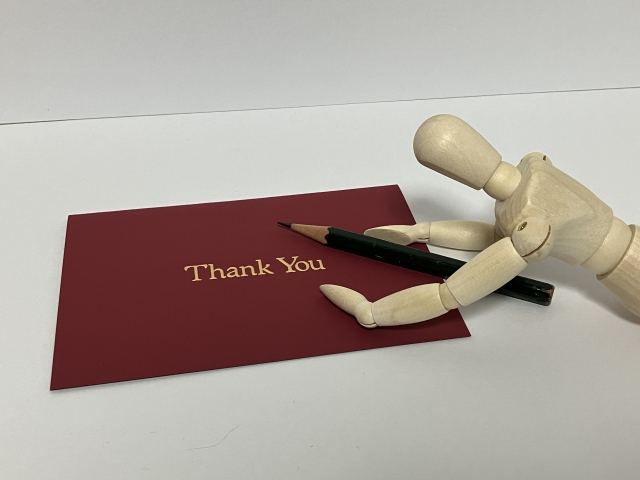
なぜ「期待」を伝える必要があるのか?
管理職の中には、こんな風にお考えの方もいらっしゃいます。
「あえて口にしなくても、仕事を任せている時点で期待は伝わるはず」
「期待を言葉にして、部下にプレッシャーを与えたくない」
よく顔を合わせている部下だからきっと伝わる。そのお気持ち、よくわかります。
しかし、こうした“言わなくても大丈夫”は、実はとても危険なのです。
なぜなら、部下にとって“言葉で伝えない上司”は、
- 「評価されてるのかわからない」
- 「何を考えているのかわからない」
- 「方向性が見えない」
だからこそ、意識をして「部下への期待を言葉にして届ける」ことが重要です。
ただし、伝える内容とタイミング、そして“相手の状態”によって、伝え方を変える必要があります。
「期待の言葉」がプレッシャーになるのは、こんなとき
期待の言葉は“信頼の証”ですが、受け取り手によっては逆効果になることもあります。
誰にでもとにかく「期待しているよ!がんばれ!」と言えばいい、というものではないのです。
特に注意したいのは、以下のような部下です
- すでに十分すぎるほど頑張っている人
- 責任感が強く、自分を追い込みやすい人
- 真面目で完璧主義の人
- 周囲の評価に敏感な人
- 失敗を恐れて動けなくなっている人
体力も精神力もあって、吸収力の高い若手社員ならばいいのですが、
もう何年もずっと真面目に頑張ってきていて実績を出しているベテランの方には要注意です。
よかれと思い、ずっと期待の言葉をかけていると、相手を追い詰めてしまいます。
それよりも、これまでの実績と頑張りを認める
「承認の言葉」を中心に伝えましょう。
私は、少ない睡眠時間の中でずっと頑張り続けていた時に、
「頑張りすぎてるよ」「無理するな」「肩の力を抜きなさい」と
上司からのいたわりの言葉をいただいて、とても嬉しかったのを覚えています。
褒め言葉も期待の言葉も、相手の状態に合わせて使い分けることが必要不可欠です。

【パターン別】期待メッセージの伝え方と例文集
ここからは、目的別に具体的な期待メッセージのパターンをご紹介します。
① チャレンジを促したいとき
まだ経験が浅い部下に、新たな役割を任せたいとき。
- 「この仕事は、〇〇さんにこそ取り組んでほしいと思っています」
- 「〇〇さんの力を試してみよう。チャレンジしてみてほしい」
▶ポイント:「任せる」ことが信頼の証であると伝え、
「挑戦する姿勢が大事」というニュアンスを伝えると安心感が生まれます。
② 評価が振るわなかった部下に向けて
厳しい評価のあと、やる気を損なわずに期待を届けたいとき。
- 「数字としての結果が出なかった。そのため、今回はこの評価になりました。ここからどう挽回するかが、私たちの課題です」
- 「今回は結果に結びつかなかった。現実を受けいれて、これから一緒に改善していこう」
▶ポイント:事実を淡々と伝えた上で、“上司も一緒に考える”というスタンスを明確に。
「頑張ってたのはわかってる」だけでは次につながる期待になりません。
③ 心が疲れていそうな部下に
すでに頑張っていて、肩に力が入っているタイプの部下には、寄り添う言葉を伝えましょう。
- 「〇〇さん、いつもありがとう。最近、少し休みながらやっていこう」
- 「すでに十分やってくれているよ。だからこそ、無理はしてほしくない」
▶ポイント:期待ではなく、“承認”のメッセージを。
「もうすでにあなたは頑張っている」という評価といたわりの言葉を届けることが大切です。
④ 若手や成長途上の部下に
伸びしろのあるメンバーには、「変化」と「成長」を見ていることを具体的に伝えます。
- 「〇〇さん、この半年でずいぶん成長したね。次はどんなことに挑戦してみたい?」
- 「小さな積み重ねが、着実に〇〇さんの力になっているよ。これからが楽しみです」
▶ポイント:「あなたの変化に気づいている」が何よりの期待のメッセージになります。
⑤ すでに役職もあり、結果も出している部下に
もうすでに結果を出していて、やる気もあるタイプの方には承認の言葉を伝えましょう。
「もっと頑張れ」など、“上からの過剰な期待”を乗せると、かえって潰れてしまう可能性があります。
- 「〇〇さんが支えてくれているおかげで、全体がうまく回っている。ありがとう」
- 「〇〇さんは結果を出せる方。ご自身のペースで着々と進めていきましょう」
▶ポイント:今の結果に対する承認の言葉、相手の力を信じて「任せる」ことを伝える。

評価の場では「事実+共に考える姿勢」
面談や査定で部下の評価が低いことを伝えるとき、悩まれる方は多いです。
ここで最も大切なのは、「感情ではなく事実を伝える」こと。
➁でもお伝えしていますが、事実は淡々と伝えることが必要です。
変にフォローしたり、オブラートに包むと伝わりきらないことがあります。
事実を伝えた後に、一緒に今後を考える姿勢を伝えましょう。
- 「目標の数字に届かなかったね。そのため、今回の評価はこちらです。
〇〇さんのこの経験、努力してきたことを今後どう活かして行くのか。
ここからどう変えていくかが大事。一緒に考えていきましょう」
このように、ただ部下に評価を突き付けるのではなく、“共に向き合う”ことも伝えましょう。
部下の課題は、上司の課題です。
▶補足:
良くない評価に対して、落ち込んだり反発したりする部下もいます。
落ち着いて対応ができるように、準備をしておきましょう。
評価の理由を伝えること、今後を見据えた話までしておきましょう。
上司の自己承認力が、部下育成の鍵を握る
「期待しているよ!」「頑張ってね!」
部下のやる気を上げるための上司の言葉が空回りするのは、「上司自身が整っていない」ときです。
部下に言葉をかけるとき、あなた自身の精神状態、健康状態は整っているでしょうか。
不安・焦り・イライラの状況で「とりあえず耳障りの良い言葉を並べる」
それでは、どんなにきれいな言葉を使っても、部下には響きません。
部下を支えるためには、上司の自己承認力の高さがポイントとなります。
- 自分の頑張りを自分で認めること
- 自分の感情を整えられること
- 部下のミスを“自分の課題”として受け止める器
上司が発信したものがチームの空気をつくります。
部下のこと=自分自身のこと。
そう考えられる上司は、部下を伸ばす力が圧倒的に高いのです。
まとめ:期待を伝える力を高めよう
いかがでしたでしょうか。「部下への期待のメッセージ」は、ただキレイなセリフを言ったところで相手にはうまく伝わりません。
今は、「期待」を伝えるときなのか。「信頼」を伝えるときなのか。
「承認」や「労い」を伝えるときなのか。
日頃から部下をよく見て、状況を把握している上司だからこそ、相手にぴったりの言葉を選ぶことが出来ます。そして、その言葉は必ず部下に届きます。
ぜひ、あなたの「伝える力」を、一緒に高めていきましょう。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

