こんにちは!
自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
「リーダーシップ」「オーナーシップ」
これらの言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。あなたはどんな風に使われていますか?
どちらも“主体的に動く人”という意味を持ちますが、簡単に表現をすれば
リーダーシップは「人を導く力」
オーナーシップは「自分ごととして引き受ける力」。
メンバー全員がこの2つの力を高めたとき、チームは大きく動きます。
今回は、言葉の本来の意味を整理しながら、
「リーダーシップ」と「オーナーシップ」の違い、
そして現場でそれを育てる3ステップをお伝えします。
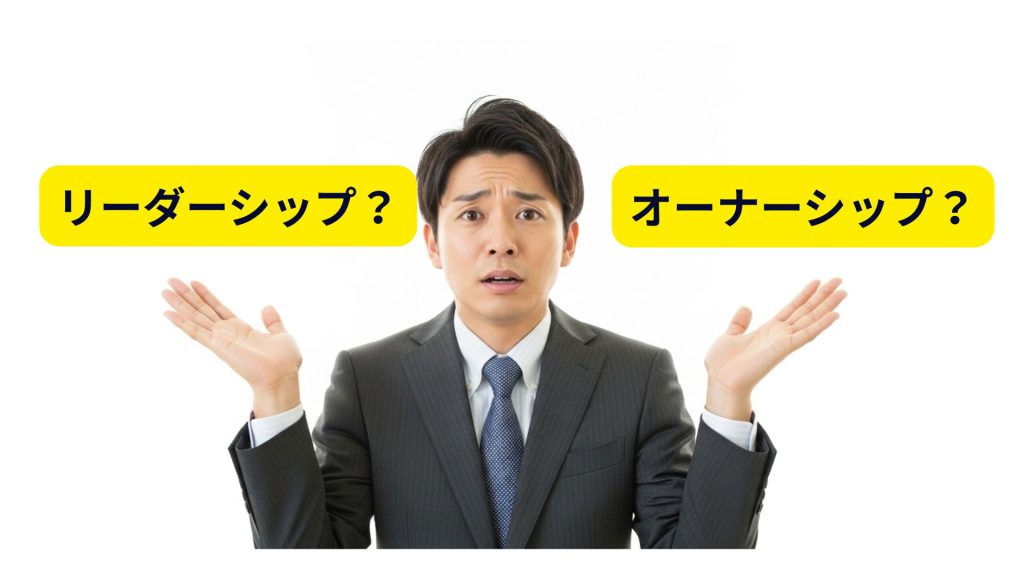
リーダーシップとは? “人を導く力”の原点
まずは「リーダーシップ」という言葉から整理してみましょう。
語源は、英語の lead(導く) に、状態や資質を示す -ship がついたもの。
つまり「人を導く資質」「方向を示し、影響を与える力」を意味します。
リーダーシップを持つ人は、目的地を示し、チームをまとめ、意思決定を担います。
周囲を巻き込みながら、行動を促し、ゴールへと導く存在です。
「人を動かす力」「信頼を得て前に進む力」
これがリーダーシップの本質です。
リーダーシップは肩書きに関係なく、
「自分が責任を持ってチームを前進させたい」と思った瞬間に、誰もが発揮できる力と言えます。
リーダーシップについては、以前も詳しく記事に取り上げていますのでこちらをご覧ください。
オーナーシップとは? “自分ごと化”の力
次に、もう一つのキーワード「オーナーシップ」について見てみましょう。
英語の ownership は、もともと「所有していること」「持ち主である状態」を意味します。
しかしビジネスの世界では、そこから転じて、
「自分の仕事やチームの成果に対して、主体的に責任を持つ姿勢」
という意味で使われるようになりました。
世界的企業のAmazonでも、リーダーシップ原則のひとつに
“Leaders are owners.(リーダーはオーナーである)”という言葉があります。
これは「自分の領域だけでなく、会社全体の成果に責任を持つ意識を持て」という考え方です。
つまり、オーナーシップとは、
「与えられた仕事をこなす」ではなく、
「チームや組織全体の成果を自分のこととして考え、行動する」意識なのです。
「オーナーシップ」よくある誤用と本来の意味の違い
| よくある誤用 | 本来の意味 |
|---|---|
| 責任を“持たされる”こと | 責任を“自ら引き受ける”こと |
| 自分の仕事だけに集中する | 組織全体を自分ごととして考える |
| 指示を待つ | 自分から課題を見つけ、動く |
| 「ミスしたら叱られる」意識 | 「どうすれば防げるか」を考える意識 |
オーナーシップとは、「責任感」よりも一歩深く、“当事者意識”と“改善意識”の掛け算なのです。
経営者目線で考える、オーナーシップの本質

経営者様とお話しをする中で、こんな話題になったことがあります。
「社員には、自分の仕事を経営の一部として捉える意識を持ってほしい」
この言葉を聞いたとき、私は「オーナーシップ=自分ごと」の意味が腑に落ちました。
たとえば、他部署でトラブルが起きたとき、
「うちは関係ない」「あの部署の問題だ」と思うのか。
それとも、
「うちでも同じことが起きないように仕組みを見直そう」と考えるのか。
この違いが、会社全体を自分事にしているオーナーシップのある人、そうでない人を分けます。
“対岸の火事”を自分ごとにできるかどうか。
それこそが、役職関係なく経営者目線で働くということです。
オーナーシップを持つ人の特徴
- 問題を他責にせず、「自分にできること」を探す
- 部署や役割を越えて、チーム全体の成果を意識している
- トラブルを見たときに、「うちは大丈夫か?」と自ら点検する
- 指示を待たず、自分から改善策を考えて提案する
このような人は、組織の中で信頼されるだけでなく、
周りに良い影響を与え、チームを静かに引っ張っていきます。
オーナーシップとは、上司や経営層に与えられる力ではなく、
“誰もが自分の意思で発揮できるリーダーシップの形”なのです。
リーダーシップとオーナーシップの違い
| 視点 | リーダーシップ | オーナーシップ |
|---|---|---|
| 意味 | 他者を導く力 | 自分の仕事に責任を持つ力 |
| 対象 | チーム・組織・他者 | 自分・自分の役割 |
| 本質 | 影響・方向づけ | 当事者意識・自律 |
| 発揮する立場 | 主にリーダー層 | 全メンバー |
| ゴール | チームを動かす | 自分を動かす |
リーダーシップが「外に向かう力」なら、
オーナーシップは「内から生まれる力」。
そしてこの2つが重なったとき、
チームは「上司に動かされるチーム」から「自分たちで動くチーム」へと変わります。
オーナーシップを育てる3ステップ

では、どうすれば職場でオーナーシップを育てられるのでしょうか。
それは「相手を信頼して、自分自身で考えられるように導くこと」です。
ステップ1:目的と背景を伝える “Why”の共有
仕事を任せるときには、やること(What)だけでなく「なぜ(Why)」を共有します。
たとえば、
「この資料を作って」ではなく、
「次の会議で意思決定を進めるために、要点をまとめてほしい」と伝える。
目的を理解している人は、仕事を“作業”ではなく“価値のある行動”として捉えられるようになります。
ここからオーナーシップは芽生えます。
ステップ2:裁量と承認をセットで与える
人は「信頼されている」と感じたときに、自ら責任を引き受けるようになります。
ただし、完全に放任するのではなく、小さな裁量(決定権)と確認の場をセットにします。
- 小さな決定を任せる
- 自分で考えた案を採用する
- 結果だけでなくプロセスを承認する
これを繰り返すことで、成功体験が自信になり、「自分にもできる」という自己効力感が育ちます。
ステップ3:情報を共有し、全体感を持たせる
オーナーシップを育むには、情報共有が欠かせません。
チームや会社の目標、数字、方針を共有することで、メンバーは自分の仕事が全体にどうつながっているかを理解できます。
「自分の仕事が会社の成長と関係している」
この実感こそが、当事者意識を生み出します。
まとめ:自分を導き、他者を導くチームへ
いかがでしたでしょうか。
リーダーシップは「他者を導く力」。オーナーシップは「自分を導く力」。
どちらか一方ではなく、この2つをバランスよく育てることが重要です。
今日からできる一歩は、「自分の働き方が会社経営に関わっている」と意識をしてみること。
その積み重ねがあなた自身のオーナーシップを育て、チーム全体の力を引き上げていきます。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

