こんにちは!自己承認力®コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
前回のコラムでは「リーダーシップとは何か?」を整理し、日本語での言い換えや現場での使われ方をご紹介しました。
では実際に、管理職として「リーダーシップをとる]とはどんな行動を意味するのでしょうか。
リーダーシップのあり方はさまざまです。声を張り上げて引っ張る人もいれば、静かに背中で示す人もいます。正解は一つではありません。だからこそ大事なのは、「自分なりのリーダーシップの型」を見つけることです。
今回は、管理職の方が明日から実践できる「リーダーシップをとる方法」を5つに整理してご紹介します。自己承認力の観点も交えながら、一緒に考えていきましょう。
1. 自分が目指すリーダーシップ像を言語化する

リーダーシップを発揮する第一歩は、「自分がどんなリーダーを目指すのか」を明確にすることです。
「率先して動くリーダー」なのか、「調整役に徹するリーダー」なのか。曖昧なままでは、どんな行動をとればよいか迷いが生まれます。
自己承認力を高める上でも、この作業は欠かせません。自分の強み・弱みを認め、自分に合ったスタイルを描くことが、結果的に無理のないリーダーシップにつながります。
実践のヒント
- 「自分が尊敬するリーダー像」を3人挙げ、その共通点を書き出す
- 「部下にどう思われたいか」を一文で表す
- それを部下にも共有し、「私が目指すのはこんなリーダーです」と伝えてみる
あるあるなのですが、「自分で考えて動ける部下を育てたい」という上司が、何でもかんでも部下に細かく指示を出していたり…
「部下から意見が出なくて困る」という上司が、会議などの場で部下を否定する言葉を繰り返していたり…
“目指したいリーダー像”と実際の自分の行動が合致しているかを確認することが大事です。
2. チームの方向性を示す
リーダーシップとは「人や組織を目標達成に導く影響力」です。つまり、方向性を示さなければリーダーシップは成り立ちません。
忙しい現場では、つい「とりあえずこれをやって」と短期的な指示を出してしまいがちです。しかし、ゴールが見えない仕事は部下のモチベーションを下げます。
実践のヒント
- 「この仕事は何のためにやるのか」を必ず添える
- 会議では「ゴールを一言で言うと?」と最初に整理する
- 部下の意見を取り入れて「みんなで決めた方向性」にする
方向性を示すのは、上司の責任です。ここを意識するだけで、部下は安心して動けるようになります。
3. 率先して動く
リーダーシップの基本は「率先垂範」。特に変化が求められる場面では、上司が最初に動くことでチーム全体の空気が変わります。
ただし、何でも自分でやるのは「リーダーシップ」ではなく「抱え込み」です。大切なのは、最初の一歩を見せること。
実践のヒント
- 新しい取り組みは上司がまずやってみせる
- 難しいタスクに挑戦する姿を見せ、「失敗も学びになる」と伝える
- 部下が疲れているときに、自ら小さな雑務を引き受けて士気を高める
自己承認力を高めている上司は、自分の挑戦を認められるため、失敗を恐れずに率先できます。
メンタルケアに関しても意識をなさってみてください。

4. 部下を承認し、成長を支援する
リーダーシップは「人を動かす力」とも言われます。けれど、人は指示だけでは動きません。「自分は認められている」「信頼されている」と感じるとき、部下は力を発揮します。
承認は、自己承認力®の要でもあります。上司自身が自分を承認できていないと、部下の承認もぎこちなくなりがちです。
実践のヒント
- 成果だけでなく「過程」や「努力」を言葉にして伝える
- 「ありがとう」「助かったよ」を毎日口に出す
- 成長の変化を具体的に伝える(「この1か月でスピードが上がったね」など)
承認の積み重ねが、部下の自己承認力を高め、チーム全体の力を底上げします。
5. 信頼関係を育てる
最後に欠かせないのが「信頼関係」です。信頼がなければ、どんなに正しい指示も響きません。
信頼関係は、一度の大きなイベントでは築けません。日々の小さな関わりの積み重ねが土台となります。
実践のヒント
- 挨拶・声かけを欠かさない(「今日はどう?」と一言添えるだけでもOK)
- 自分の失敗談や弱みをオープンにする
- 約束は必ず守る(小さな約束ほど大事にする)
そして、私が現場で気を付けているのは「相手に合わせる」ということです。
たとえば、若手や新人ばかりのチームであれば、仕事を楽しめるように雰囲気を盛り上げることを重視します。
一方、実力はあるけれど控え目な方が多ければ、意見を引き出すためにヒアリングを大切にします。
ベテランで自己主張が強い方が集まる場合には、それぞれの意見を尊重しつつ、全員が協力できるように促します。
また、エネルギーが低めでなかなか動きが鈍いチームでは、タスクを細かく分けて渡し、こまめにコミュニケーションをとりながらエンジンをかけていきます。
このように、メンバーの状況や個性に合わせてスタイルを変えることが、信頼関係を築き、リーダーシップを発揮するうえで大切だと実感しています。
まとめ:自分らしいリーダーシップを
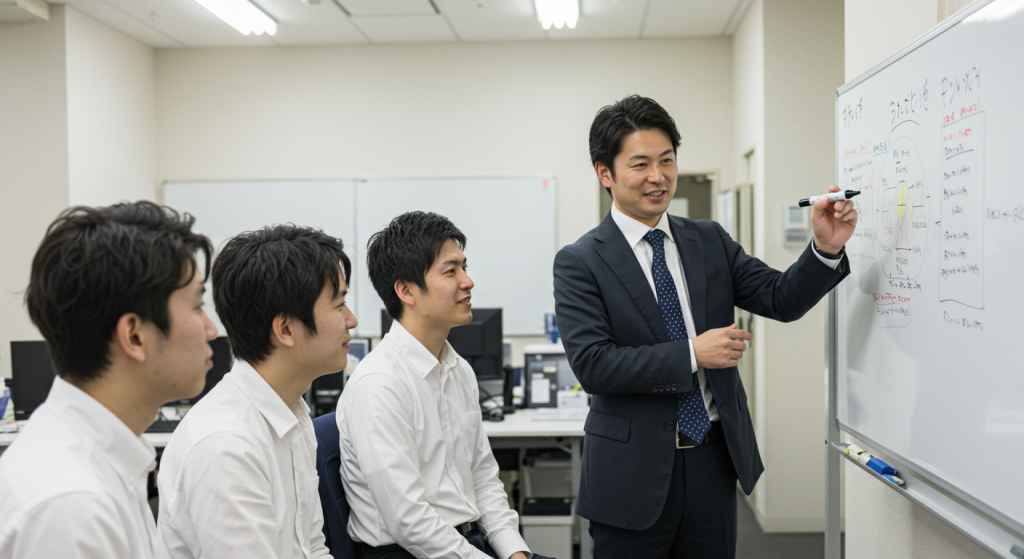
リーダーシップの取り方は一つではありません。
今回ご紹介した5つの実践方法
- 自分が目指すリーダーシップ像を言語化する
- チームの方向性を示す
- 率先して動く
- 部下を承認し、成長を支援する
- 信頼関係を育てる
これらを通して、自分なりのスタイルを磨いていきましょう。
自分が思い描くリーダーシップの取り方と、相手に合うリーダーシップの取り方を見極めることです。
リーダーの役割であり特権は「決断」。
「笑顔が絶えないチームにする」
「お客様を喜ばせる」
「成果を出す」
そんな自分の軸をぶれずに持っていれば、具体的なやり方はこだわらなくても大丈夫。
あなたらしいリーダーシップが、きっと周囲を前に進める力になります。
まずは今日、「自分が大切にしたいリーダーシップの軸」を一文で書き出してみましょう。
その小さな一歩が、リーダーとしての未来を大きく変えていきます。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

