こんにちは!自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
「うちの部下、最近明らかに余裕なさそう…」
「いやいや、この程度もこなせないなんて正直ガッカリ…」
このコラムを開いてくださったあなたは、部下の方にこんな複雑な想いを抱えていらっしゃるかもしれません。
そして、同時にこうも思うことはないでしょうか?
「この状態って、もう部下の能力の限界?それとも甘えてるだけ?」
「上司である自分のマネジメントに問題があるのか…」
ご想像のとおり、部下のキャパオーバーは、部下だけの問題ではありません。
そこには、部下本人の性格や行動傾向に加え、上司であるあなたの関わり方、そして上司自身の「余裕のなさ」も影響している可能性があります。
本日は、「部下のキャパオーバーを見極め、支える」ための具体的な5つの対策をお伝えいたします。
さらに、自己承認力の観点も含めた「上司自身がキャパオーバーにならないための気づき」も交えてお届けします。
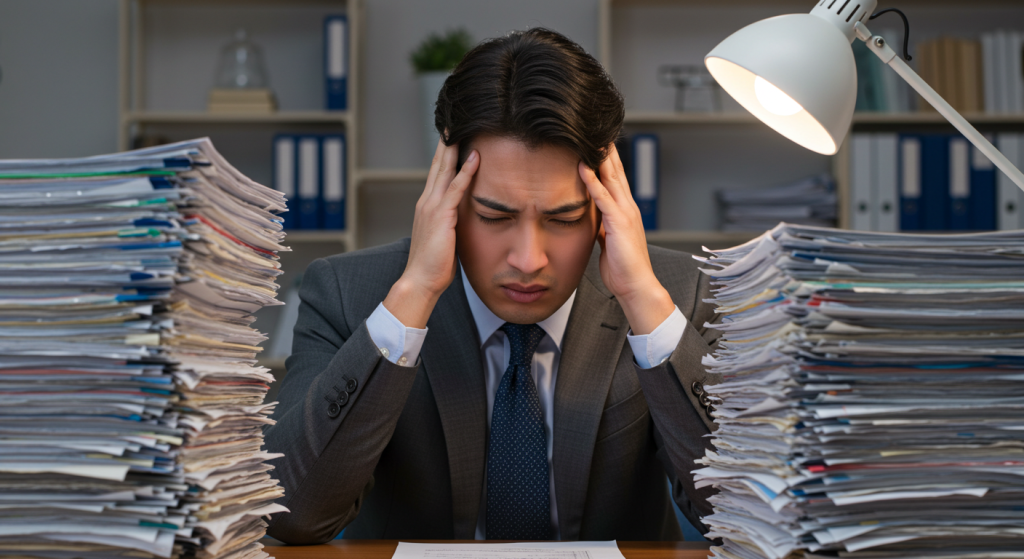
キャパオーバーになりやすい部下の特徴
まず大前提として、部下のキャパオーバーは、大半の場合は「能力が低い」わけでも「やる気がない」わけでもありません。
こんな特徴を持った方が多いのです。
- 責任感が強い、あるいは気の弱さで「断れない」
- 真面目で完璧主義
- 周囲からの期待に応えたい気持ちが強い
- 頼まれると嬉しいが、負担も溜め込みがち
- 困っていても「大丈夫です」と言ってしまう
最初の頃は、「出来る部下」「優秀な人材」と言われてうまくやってきたタイプほど、自分の限界を認めることが苦手です。
周囲も「この人なら任せても大丈夫」と頼りがちになるため、
本人すら気づかぬうちに“静かな限界”に向かっていることが多いのです。
次の章からは、部下がキャパオーバーして手遅れになる前の対策5つをご紹介します。
1.変化のサインを見逃さない“観察力”をもつ
一つ目は、観察力です。
「うちの部下、なんだか様子がおかしくなった」
そんな“違和感”を感じるためには、観察力が必要です。
キャパオーバーの兆候は、大きな異変ではなく、日常の中の“わずかな変化”として現れます。
◆ こんなサインが出ていませんか?
| サインの種類 | 具体的な変化 |
|---|---|
| 行動の変化 | 報告が遅れる、集中力が続かない、遅刻・早退が増える |
| 態度の変化 | 表情が固い、声のトーンが低い、笑顔が減った |
| 言葉の変化 | 「すみません」「忙しいです」を繰り返す、無言が増える |
| 精神的変化 | イライラしやすい、注意に過敏、冗談が通じない |
| 身体の変化 | ため息、顔色、体調不良の申告が増える |
これらは、部下からの無言のSOSです。
「もう限界」と言えない人ほど、こうした“にじみ出る変化”で助けを求めているのです。
詳しくはこちらのコラムで書いていますので、チェックなさってみてください。
→【部下がメンタル不調?SOSのサインと解決策】

2.“棚卸しミーティング”で優先順位を一緒に整える
現在、部下が抱える仕事量を把握していますか?
真面目な部下ほど、「全部やらなきゃ」と完璧を目指し、抱え込んでしまいがち。
その結果、重要な仕事が後回しになり、ミスや遅延につながることも少なくありません。
仕事はチームで行うもの。上司のサポートは必須です。
対策を打つには、まずは現状把握から。仕事の棚卸しを定期的に行いましょう。
◆ 対策:週1回5分でも「棚卸し時間」をとる
「今どんなタスクを持ってる?」
「この中で優先すべきものはどれ?」
「いつまでに出来そう?」
「これは、そもそも本当に必要?」
こうした“仕事の棚卸し”を一緒にすることで、優先順位を再整理できます。
部下の視野が広がり、「これは後回しでいい」と判断できるようになることも。
そして上司にとっても、「なぜ終わらないのか?」ではなく、「どれだけの仕事を抱えていたのか?」に気づく良い機会になります。
減らす勇気をもつ
上司の立場になると、「任せる」「成長させる」ことに意識が向きますが、時には“やらない”判断も必要です。
例えば
・過去の慣習でなんとなく残っている業務
・他部署からの非公式な頼まれごと
・「ついでにお願い」の積み重ね
こういった業務に振り回されていないでしょうか。
一つ一つは小さなことでも、このような「見えない負担」が部下のキャパを圧迫していることがあります。
3.時間の使い方、教えていますか?

ここからは、「そもそも教えていたか?」という視点で見ていきましょう。
これまでの対策では、“今の仕事量”にどう向き合うかを考えてきました。
一度考えていただきたいのですが、「そもそもどう動けばいいか」「どんな順番でやればいいか」を、部下の方はご存じでしょうか。
「部下が時間の使い方や目標管理の基本を学んでいない」
そんな方がキャパオーバーになるのは当然です。
時間管理やスケジュール管理、目標設定の技術は、すべて「スキル」です。
才能ではなく、教えられれば誰でも伸ばせる力です。
私自身の経験談をご紹介します。かつて飲食店で勤務していた時に、こんなことがありました。
開店準備に、いつもシフト時間よりも30分~1時間も早く来るアルバイトさんがいたのです。理由は仕事が間に合わないから。私を含む他のパートさんたちは、シフト時間通りで問題なくこなしていました。
朝が早い出勤は身体にも負担が大きいので、一度そのアルバイトさんと一緒に、開店準備の工程をすべて「時間で洗い出す」ことにしたのです。
「鍵を開けて、電気をつけて、手を洗って……これで何分かかる?」
「フキンを消毒して洗って、台を拭くのに何分?」
「冷蔵庫から食材を出すのに何分?」
本当にこのレベルで、細かい工程まで丁寧に確認しました。
本人が想定した時間を、少し余裕をもって設定しながら、開店準備のタイムスケジュールを一緒に可視化しました。
結果、次の日に彼女は「時間通りに動く」チャレンジに成功しました。
彼女が時間通りに仕事が出来なかった原因は…能力が低いわけでも、手が遅いわけでもありませんでした。
無駄な動きが多かったことだったのです。
慎重な彼女は、何かひとつ作業をするたびに「次は何だっけ?」と毎回迷いながら、あちこちに動いていたことを自覚したようでした。
このように、「ただ教えていなかった」だけで、キャパオーバーに感じてしまうケースは多々あります。
見える化し、一緒に組み立てていけば、部下はちゃんと力を発揮できる。
その視点を、上司である私たちが持てるかどうかが大切です。
- 本当に必要な仕事か?
- 他者に任せられないか?
- 自動化や効率化できないか?
上司と部下が目線を合わせながら、これらを一緒に考えることをおすすめします。
4.“雑談”は信頼の投資。余裕のない時こそ話しかける
部下の方と雑談をしているでしょうか。仕事を中心とした話題でも構いませんが、報連相以外の会話はありますか。
一つの話題に対して、「あなたはどう思う?そうか、自分はこう思う。」
こういったやりとりを重ねることがお互いの価値観を知ることに繋がります。
「忙しそうだから、話しかけるのはやめよう」
部下の方にそう思われてしまうことで、情報が入ってきにくくなります。
雑談は、ムダな時間ではありません。
上司とコミュニケーションをとることで
「自分はちゃんと見られている」「気にかけてもらえている」という安心感が生まれます。
まずは気軽に話しかけてみましょう。
「Aさん、おはよう。出張ありがとうね。〇〇さんの様子どうだった?」
「Aさん、お疲れ様。最近、どう?」
「Aさん、お疲れ様でした!~の作業、大変だったでしょう?」
上司から話しかける回数が多いほど、部下からも声をかけやすくなります。
5.“限界前”に声が出せる職場づくりを!
いざという時に、「もう無理です」と言えない職場ではありませんか。
それは、キャパオーバーが“爆発”してからようやく発覚する環境です。
「限界まで頑張ってからじゃないと、助けを求めてはいけない」
そんな空気があると、部下は我慢し続け、心身に異変が起こってしまいます。
私は過去に、頑張りすぎてキャパオーバーになり、メンタル不調になった時期があります。
そのときは毎日、追い込まれていて「病気になれば、仕事を休めるのに…」と考えるまでになっていました。誰にも相談できず、辛い、しんどいと言えなかったのです。
◆ 対策:普段から“頼っていい”空気を作る
- 「無理なときは無理って言っていいんだよ」
- 「忙しいなら一言くれると調整するよ」
- 「困ったときは、手を貸すから遠慮しないでね」
この声がけは、部下を甘やかすのではありません。頑張りすぎる部下には、こういった“事前の声かけ”をすることで、安心して助けを求められる土台になるため重要なのです。
【実はあなた自身も…】上司のキャパオーバーが部下に伝染する

ここまでお読みになって、「うちの部下がまさにこれだ」と思われた方へ。
あなた自身もキャパオーバー気味ではありませんか?
- 部下の変化に気づけない
- イライラしやすくなった
- 自分の時間が取れない
- 「こんなことで相談してこないで」と思ってしまう
この状態ならば、要注意です。
上司も人間です。感情も波もあります。
誰かのことを支えるためには、まず自分の“心の余白”が必要です。
この「心の余白」をつくるために、自分自身をねぎらい、認める習慣をつけましょう。
自己承認力は部下のためだけでなく、上司自身のためにも必要な力です。
【まとめ】見極め、支え、自分も満たす“本当のマネジメント”
いかがでしたでしょうか。
キャパオーバーは、ある日突然起きるわけではありません。
小さな積み重ねの末に「限界」を迎えるのです。
だからこそ、“手遅れになる前のサイン”に気づける上司が、組織を守ります。
そしてもうひとつ。
上司ご自身が「自分のキャパシティ」も意識できていれば、
人に優しくできる余裕が生まれ、結果的にチーム全体が穏やかで前向きになります。
部下だけでなく、あなた自身の頑張りにも目を向けていきましょう。
部下のためにここまで考えているあなたは、十分すぎるほど“熱心でいい上司”です。
今日から始められること。
まずは一言、「最近、調子どう?」と柔らかい表情で
部下に声をかけるところから始めてみてはいかがでしょうか。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

