こんにちは!自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
「部下の上手な叱り方」
ビジネス研修や講座で、長年人気のテーマです。
それだけお困りの方がいらっしゃるということですよね。
「部下を叱るのが苦手です」
「どうやって叱ったらいいですか?」
私も以前はとっても悩んでいましたし、多くの上司の悩みの種かと思います。
実際に、受講者様からの「部下の叱り方」に関するご相談はとても多いです。
そのときに私がお答えしているのは、とってもシンプル。
「部下を叱る必要はありません」
こうお答えすると驚かれるのですが、職場の大人同士のやりとりで「叱る」ことは本当に必要でしょうか。考えてみると「叱る」場面は、ごくごくわずかなのです。
よほどのルール違反やモラル違反でない限り、
叱らなくても、部下は行動を変えることができます。
では、実際にどんな声のかけ方があるのか?
今回はこちらをテーマにお伝えいたします。
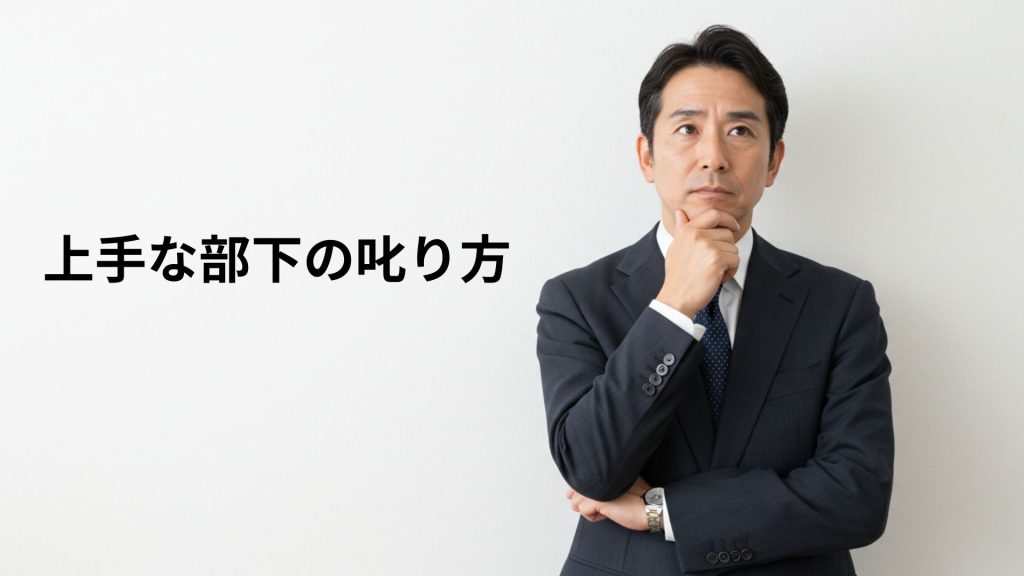
怒る・叱る・導くの違いを意識していますか?
まず初めに確認をしておきたいのが、言葉のつかいわけです。
色んな表現の仕方をするかたがいますが、こちらのコラムではこのように統一いたします。
- 怒る:自分のため。感情を発散させたい。相手を責める。
- 叱る:相手のため。改善してほしい点を伝える。
- 導く(指導する):相手とチームのため。ゴールに向けて伴走する。
一般的に連想される「叱る上司」は、多くの場合は「怒っている」のではないでしょうか。
「怒る」とは、感情的に声を荒げたり、相手のダメ出しをすることです。
怒られた部下は委縮し、表面上は従っても、心の中では上司と距離を置きます。
そして、また同じことを繰り返してしまう…
「叱る」は、冷静に伝え方を相手に合わせながら「改善してほしい点を伝えること」です。
親が子を叱るのは、子のためですよね。
意図的に声のトーンを落としたり、表情などの工夫をしながら
「~してほしい」「~はやめて、こうして」と伝えるのは叱る。
危険があったり、ルールやモラルを逸脱した方に対しては、こちらの手法を使います。
導く方法では、少し伝わりにくいからです。
「導く・指導」は、相手を否定せず、一緒に行動を変えるための最短ルートを考えて、ゴールに導くことです。
一緒に同じゴールを目指すという考え方
部下の行動を正すときも、上司と部下は同じゴールを目指すチームメイトです。
たとえば遅刻が多い部下の場合、
「何回遅刻すれば気が済むんだ!」こんな風に怒鳴ったとして、すぐに改善する可能性は低い。
部下育成の面でみると、上司は感情的にならずに
「本人も遅刻はしたくないが、自分だけでは改善できない」と捉えてみるのがおすすめです。
そして、「どうやって遅刻をなくしていくか」を一緒に考えます。
部下が改善すべきことは、上司も改善すべきことなのです。
「このままじゃ社会人としてまずいよな、信頼も失うぞ。どうしようか」と、問題解決の仲間として向き合うのです。
ここで重要なのは、上司が「正解を与える側」にならないこと。
「早く寝ろ」「目覚まし時計を増やせ」など、一方的に解決策を押し付けるのではなく、本人が納得して行動できる方法を探すことです。
【事例】「やる気ない」と言われ続けた部下の本当の理由

ここで、一つのエピソードをご紹介します。
ある企業様で、若手社員が仕事中にたびたび眠ってしまうことがありました。
周囲からは「やる気ない」「居眠りするなよ」と言われ、上司からも叱責を受けていました。
しかし、一向に改善されないまま、その社員の立場は日に日に悪くなっていきました。
そんな話を耳にして、私は一度、その社員の方にじっくり話を聴くことにしました。
いざ、本人と向き合って話をしてみると、「本人もどうにかしたい」と思っていることがわかりました。
徐々に本音を言葉にしながら、ぽろぽろと涙を流すほど、本人も辛い思いをしていたのです。
社員の方の話を聞いていく中で、私の頭をよぎったのは…睡眠障害。
その可能性を彼に伝えて、一度病院に行くことをアドバイスしました。
その後、彼は医師の指導を受けながら、睡眠環境や生活習慣の見直しを続けることになりました。すると、症状が改善していき日中の居眠りがなくなったのです。学生時代からの悩みがなくなったと言います。
長い間、周りから「やる気がない」と見られてしまうのは苦しかっただろうなと想像します。
これは上司が部下を一方的に怒る・叱るでは、解決できなかった事例です。
相手に伴走して、一緒にゴールに向かっていく「導く」を部下育成の土台にしていると、思いもよらない解決法が見えてくるのです。
それでも「叱る」必要がある2つのケース
とは言え、上司が部下を「叱る」場面が全くのゼロというわけではありません。
次のような場合は、明確な線引きと毅然とした対応が必要です。
- ルール違反
法令や社内規定、契約など明確なルールを守らない場合。
例:情報漏洩、コンプライアンス違反。 - モラル違反
人を傷つける、信用を損なうなど信頼関係を崩す行為。
例:差別発言、ハラスメント行為。
この2つは、本人の成長だけでなく、チームや会社を守るための「最終手段」として叱る必要があります。
ただし、この場合も感情で怒るのではなく、あくまでも事実と影響、改善策を冷静に伝えるようにしましょう。
タイプ別:叱る場面にも応用できる「導き方」8選

叱らざるを得ないときにも、日常の指導にも使えるタイプ別アプローチです。
それぞれに会話例とNG例を入れてみました。
1. 慎重派タイプ:安心+改善
会話例:「まず○○はよくやってくれたよ。その上で、□□を意識してくれるともっと良くなる」
NG例:「どうしてこんなに遅いの?」→不安が増し、萎縮する。
2. 積極派タイプ:即時フィードバック
会話例:「行動力すごいね、助かってる!今回は□□にだけ気をつけよう」
NG例:後日まとめて複数点を注意→次の行動にも同じミスが出る。
3. マイペースタイプ:影響を説明
会話例:「△日までに進めよう。この作業が遅れると□□に影響するんだ」
NG例:「急いでやって」だけ→なぜか?理由を理解できず、優先度が下がる。
4. 完璧主義タイプ:基準を共有
会話例:「〇〇さんの仕事は、質が高いね。今の段階は、スピード優先で△時までお願いします」
NG例:「もっと早くやって!」だけ→質を落とすことに罪悪感を持つ。
5. 受け身タイプ:段階的に依頼
会話例:「まずは、△時までにこの1件を進めてみよう」
NG例:大きなタスクを丸ごと渡す→動き出せない。
6. 感情型タイプ:クールダウン
会話例:「あとで△時くらいから少し落ち着いてから話そう」
NG例:感情的になっているときに叱る→反発か沈黙しか返ってこない。言い合いになることも。
7. 自信過剰タイプ:事実と数字
会話例:「今回の結果は、目標より△%足りなかった。少しでも改善していくには何が出来そう?」
NG例:抽象的に「最近調子悪いね」→本人は危機感を持てない。
8. 新人タイプ:具体的な承認→改善
会話例:「~してくれてありがとう!次は□□を意識して挑戦してみよう」
NG例:「ここがダメだった」「ここが出来ていなかった」だけ→チャレンジ精神が失われる。
叱る前にできる4つの「導きステップ」
- 原因を聞く
行動の背景を本人の口から聞くことで、意外な事実が見える。 - 価値観を理解する
何を大事にしているか知ることで、響く伝え方が変わる。 - ルールと基準を共有する
「暗黙の了解」ではなく、明文化する。 - 改善の一歩を承認する
小さな進歩も認めることで、行動が継続する。
まとめ:「叱る」は最終手段、ゴールに導くことが重要
いかがでしたでしょうか。部下を「叱る」ことにプレッシャーを感じる必要はありません。
ほとんどの場面では、原因を理解し、行動を導き、改善を承認することで解決できます。
自己承認力が高い上司は、自分の価値を認めています。
だからこそ、部下を許容でき、相手の価値も認めることができます。
その関わり方が、「部下を導く土台」になるのです。
部下を育てる本当の力は、叱る力ではなく、導く力。
相手の話を聴き、承認し、一緒にゴールを目指していく。
部下が自ら成長したくなる、上司の関わり方をしていきましょう。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

