こんにちは!自己承認力コンサルタントの尾形さくらです。
いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
「前はよく話してくれていたのに、最近は必要最低限しか答えてくれない」
「会議でも発言が減り、雑談もなくなってしまった」
「このまま退職につながるのでは…」
上司として、このような“沈黙のサイン”に不安を感じることはありませんか?
部下が喋らなくなる背景には、「心理的な壁やSOSのサイン」が隠れているかもしれません。
楽観視して放っておくと、信頼関係の崩壊や突然の退職につながる危険もあります。
今回は、部下が喋らなくなる心理背景と、上司にできる5つの対策を、私自身の経験談も交えながらご紹介していきます。今現在お困りの方はもちろん、今後の部下の変化に備えたい方にもおすすめの内容です。
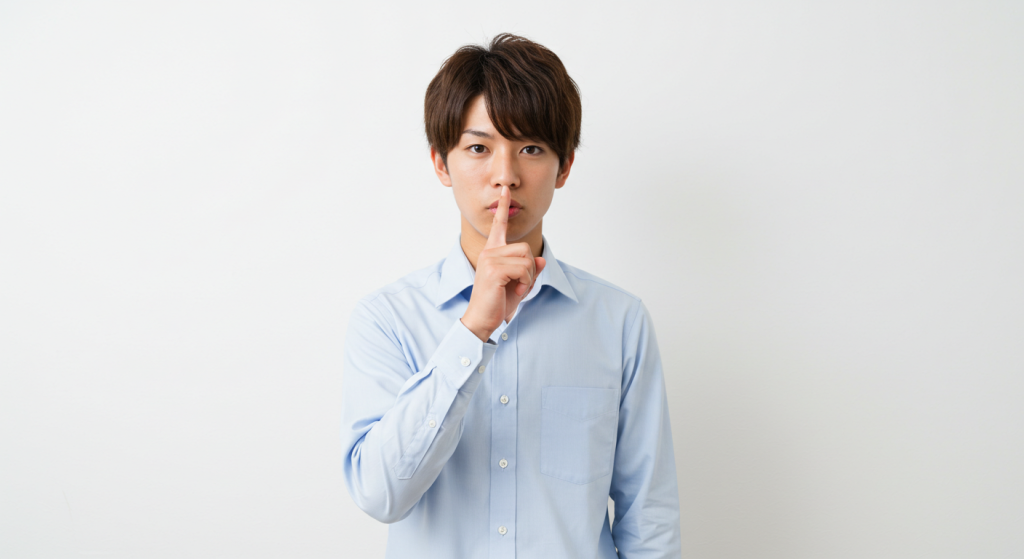
部下が喋らなくなる5つの心理背景
部下が喋らなくなる背景を考えていきましょう。相手の立場を想像してみることがとても大事です。
あなたは、どんなときに「上司と喋りたくない」と思うでしょうか。
そんな切り口から、大きく5つの心理背景をご紹介いたします。
1. 上司に話しても無駄だと思っている
提案や意見を出しても「それは違う」と否定され続けると、「どうせ言っても無駄」と感じ、沈黙を選びます。何度も経験を重ねるうちに、「自分の声は届かない」という学習が定着してしまうのです。
➡チェック:つい反射的に「いや、それは」と否定していませんか?
2. 評価が下がるのを恐れている
ミスや弱音を出したときに強く叱責された経験から、「余計なことは言わない方が安全」と考えてしまうのです。特に評価や査定を意識する時期には、防衛本能として沈黙が強まります。
➡チェック:部下の失敗を“次につなげる材料”ではなく、“評価を下げる対象”にしていませんか?
3. 自分が認められていないと感じる
努力や成果が承認されず、「自分の意見なんて意味がない」と思えば、話す気力をなくします。人は「聴いてもらえている」と感じられることで初めて安心して発言できるものです。
➡チェック:小さな努力や日々の頑張りを“当たり前”にして流していませんか?
4. 上司が忙しそうで話しかけづらい
いつもパソコンに向かい、イライラしているように見える上司に、雑談や相談を持ちかけるのは気が引けるものです。「今はやめておこう」が積み重なると、やがて会話そのものを控える習慣になってしまいます。
➡チェック:“忙しいオーラ”を無意識に出していませんか?
5. 心身の不調や退職の準備を隠している
疲労・メンタル不調・家庭の問題などを抱えながら、「仕事中は黙ってやり過ごそう」と沈黙を選ぶこともあります。すでに退職を決めている人は、関わりを減らしていく傾向もあるのです。沈黙の裏側には、本人の必死の「防衛」や「サイン」が隠れている場合も少なくありません。
➡チェック:“最近静かだな”を単なる性格のせいにして見逃していませんか?
こうした変化に気づくヒントについては、こちらの関連記事をチェックしてみてください。
私の体験談:突然喋らなくなった部下
私自身も、これまで頻繁に話してくれていたアルバイトの子が、ある日突然口をきかなくなった経験があります。無視をしているのは、どうやら私に対してだけのようでした。
「私何かしたかな?」「ご機嫌ナナメなのかな?」など、あれこれ考えてみましたが、思い当たることは何もありません。
あとから判明するのですが、彼女が私と話をしなくなった理由は、予想しないものでした。
なんと「焼きもち」だったのです。職場に好きな人がいて、その人が私と楽しそうに話していて気に食わなかったんだそうです。
思わず「知らんがな!」と心の中で突っ込みましたが(笑)、本人にとっては大きな感情だったのでしょう。
彼女と話し合う時には、こんな風に伝えました。
「私たちは仕事をするためにここに来ています。好き嫌いがあっても、お互いが気持ちよく働けるように、最低限のコミュニケーションは取りましょう」
結果的に、それ以降は通常通りになり、仕事をスムーズに進められるようになりました。
よく考えれば、10~20代の感情が豊かな時期には、業務中に感情が出ることもありますよね。
この経験から学んだのは、沈黙もひとつの感情表現。上司が冷静に線を引きつつ対話を続ける姿勢が、関係修復のカギだということです。
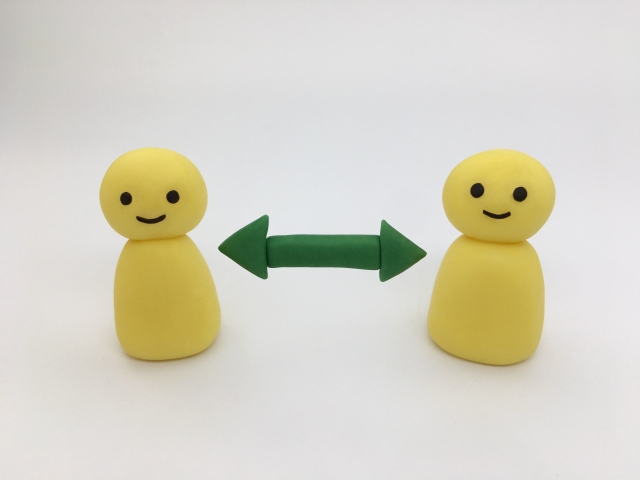
退職を防ぐ!上司にできる5つの方法
部下が黙りがちになる背景には、不安・不満・疲労などさまざまな要因が隠れています。
その沈黙を「性格だから仕方ない」と放置すると、気づかぬうちに退職へとつながってしまうことも。
ここでは、上司が日常の中でできる5つの工夫を具体的にご紹介します。
① 直感を大事にし、観察する
「最近静かだな」と感じた直感は大切です。小さな違和感の裏には、部下のサインが隠れていることが多いのです。
ただし、「絶対にトラブルがある」と決めつけて問い詰めるのではなく、まずは冷静に観察を続けましょう。表情・発言・行動の変化を見て、タイミングを見極めることがポイントです。
② 無理に聞き出さず、いつでも受け入れる態勢をつくる
「大丈夫です」と返されたら、すぐに深掘りして追及するのは逆効果です。
部下が心を開く準備が整っていない段階で聞きすぎると、防御反応を強めてしまいます。
そんなときは「そうか、分かった。何かあればいつでも言ってね」と一歩引いたスタンスを取りましょう。
数日後に「実は…」と部下から自発的に相談があるケースは多いものです。
③ 小さな承認を積み重ねる
沈黙している部下には、結果よりも日々のプロセスを承認することが効果的です。
「資料を期限内にまとめてくれてありがとう」
「昨日のサポート、助かったよ」
こうした小さな承認の積み重ねが、「この上司なら大丈夫」という安心感を育てます。
黙っている時間が多くても、“見てくれている”という感覚が信頼につながります。
④ 1on1や雑談で安心感をつくる
会議や業務連絡の場では、どうしても緊張感が漂います。
だからこそ、短時間の1on1や休憩中の雑談が効果的です。
「週末はどう過ごした?」
「最近ハマっていることある?」
など、仕事に関係ない軽い話題から入ることで、沈黙を破るきっかけが生まれます。
「この上司には何を話してもいい」と思える関係づくりが大切です。
⑤ 退職リスクを防ぐ“予防線”を張る
沈黙が続けば、退職につながるリスクがあります。
だからこそ、普段から「ここなら声を上げていい」と思える言葉を投げかけましょう。
- 「意見はいつでも聞きたい」
- 「あなたの考えはチームにとって大事だよ」
- 「一緒に改善していこう」
こうした言葉は、退職を考え始めた部下の心を踏みとどまらせる“予防線”になります。
早い段階での声かけが、信頼関係の継続につながるのです。
部下の退職のサインと対策を掘り下げた記事も、要チェックです。

まとめ:沈黙は新たな関係構築のチャンス
いかがでしたでしょうか。部下が喋らなくなると、不安や焦りを感じますよね。
しかし、その沈黙は「新たな関係を築くチャンス」かもしれません。
上司ができることをもう一度整理すると
- 決めつけず観察する
- 無理に聞き出さない
- 小さな承認を積み重ねる
- 雑談や1on1を増やす
- 日頃から退職リスクを防ぐメッセージを送る
これらをコツコツと積み重ねていきましょう。
大事なことは、「相手の態度に引っ張られないこと」だと私は考えています。
嫌われようが、無視をされようが「相手は大事な自分の仲間」
上司としての自分の軸を持って、伝えるべきことは伝え、話し合うことが大事です。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
また次回のコラムでお会いしましょう(^^)

